導入──“生きろ”と“死にたい”の交差点で
2017年に投稿されたカンザキイオリの楽曲『命に嫌われている。』は、瞬く間に多くのリスナーの心をとらえた。その理由は単純ではない。本楽曲は、一見すると反自殺的な“生の讃歌”のようにも聞こえる。しかしその実、歌詞の大半を覆うのは〈幸福がわからない〉〈死にたい〉といった否定的感情の累積である。表題の「命に嫌われている」というセンテンスにしても、それが“命を大切にしよう”という標語的命題とどれほど距離を取っているかは明白だ。
そのうえで本稿では、本作を一つの“励ましの歌”としてだけでなく、「終わってしまったものを前提に、それでも生きることを続けてしまう存在」に関する物語として捉え直したい。すなわち、筆者が独自に提唱する批評概念〈アフター系〉を軸に、『命に嫌われている。』を読み解く試みである。
〈アフター系〉とは、従来の成長物語や希望の物語が成り立たなくなった後、つまり“終わり”や“喪失”を前提としたうえで、それでもなお小さな営みや情動が始まってしまう物語群を指す。これは2020年代以降の創作に見られる新しい傾向であり、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』や『葬送のフリーレン』などに典型的に現れている。 本作『命に嫌われている。』もまた、表向きは“死にたい”という絶望に満ちた告白から始まりながらも、最後には「生きろ」と強い言葉で締めくくられる。このとき歌われている“生”は、もはや善でも祝福でもない。それは「どうしても続いてしまうもの」としての生であり、終わった物語のなかでそれでも起きてしまうアフターの感情なのである。
本論──生の残骸に立ちすくむ詩
『命に嫌われている。』は、明確な希望や救済を語らない。それは、言い換えれば「すでに希望が無効化された時代」における“語りの不可能性”そのものを抱えた作品である。
この文脈において参照すべきは、〈アフター系〉という概念である。先述したように〈アフター系〉は、物語のクライマックスや救済がすでに終わってしまったあと、その残滓の中でなお語られる営みを指す。バブル経済の崩壊、9.11以降の終末感、SNS社会の露出過多と匿名性の交差などを経た現代において、「成長」「成功」「愛」などの物語的な出口はもはや機能しなくなっている。私たちは“終わっている”という感覚の中で、なおも日々を続けてしまっている。
本楽曲では、「幸福の意味すらわからず」「命に嫌われている」といったフレーズがそれを如実に表している。ここに登場する語り手は、「どうすれば幸せになれるか」という問いすら、すでに終わったものとして放棄している。さらに言えば、「君が生きていたならそれでいい」と他者の生を願う最後の一節も、もはやエゴや利他主義では説明できない感情である。希望はない。だが、それでも言葉は生まれてしまう。
この“言葉が生まれてしまう”という事態は、〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉という概念とも呼応する。〈ネガティブ・ケイパビリティ〉とは、本来は詩人ジョン・キーツが用いた表現であり、「すぐには解決できない不確実さや曖昧さを受け入れる力」を指す。ここで筆者が用いる〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉とは、それをさらに発展させ、「わからなさ」そのものにこそ居場所を求めてしまうような欲望構造を示している。
本楽曲の語り手は、自己矛盾に満ちている。「自分が死んでもいい」と言いながら、「周りに生きてほしい」とも願ってしまう。あるいは、「死にたい」と言いながら、「ずっと一人で笑えよ」と語る他者との関係性にすがってしまう。これらは、いずれも“矛盾しているから間違っている”のではなく、“矛盾したまま生きるしかない”という地点に立脚している。 このような語りの構造こそが〈アフター系〉と〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉の交点であり、まさに“終わってしまった世界のあと”でこそ成立する言葉の在り方なのだ。すべてが意味を失っても、すべてが矛盾にまみれても、なおも「生きて、生きて、生きろ」というリフレインが響くとき、それはかつての希望の代替物ではなく、“残骸のなかから生まれた声”にほかならない。
結論──答えのない“生”を生き延びるために
『命に嫌われている。』というタイトルは、すでに命そのものを価値中立的なものと見なしている。命は祝福ではない。苦しみでもない。だからこそ「嫌われている」という感覚だけが残り、それにどう向き合えばよいのかさえ、明確な答えは存在しない。
このような地点からなお「生きろ」と語るこの歌は、“前向きな応援”とは異なる。“生きてしまうことのやるせなさ”と、“生き続けることの不可避性”が重なったとき、そこにこそ本作の真の詩学が宿る。
それは「それでも生きろ」ではなく、「生きてしまう」という事実の歌である。希望があるから生きるのではなく、絶望のなかでそれでも呼吸が止まらなかった者たちの、静かな足音のような言葉たち。 そしてその足音は、今日もどこかで誰かの呼吸に混ざりながら、また新たな語りを生む。終わった物語のあとに始まってしまう、アフターの詩として。
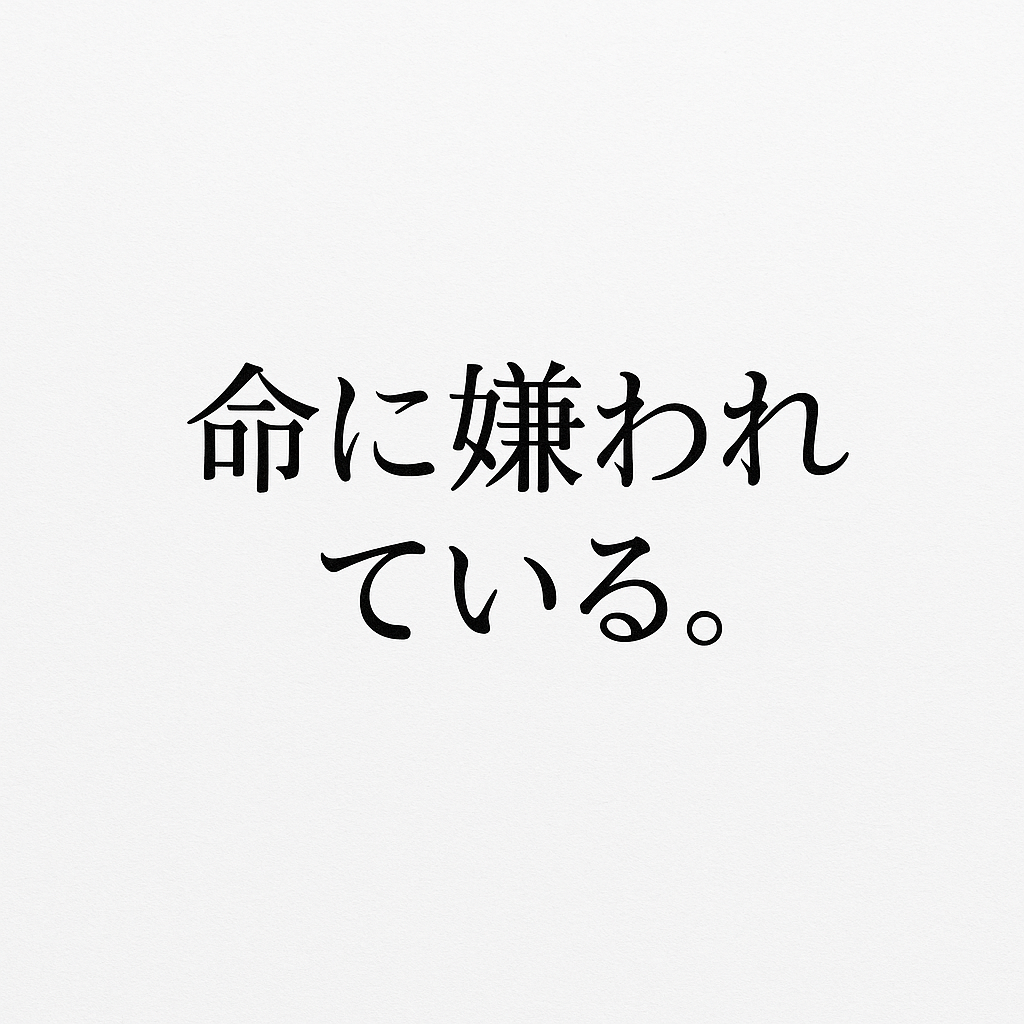
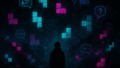
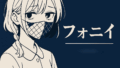
コメント