こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 本曲の「皮肉さ」をきちんと言語化したい人
- 本曲が示唆しているものを知りたい人
I. 導入――“超主人公”が量産される時代の痛覚
タイムラインが眩しい。
「成功しました」「昇進しました」「バズりました」。SNS 上に並ぶ眩しいハイライトは、常にリロードされ更新され続けている。だがその背後には、「光に溢れて、陰に居場所がない」現実が静かに積もっていく。ピノキオピーによるボカロ楽曲『超主人公』は、ヒーローと脇役という二項対立をあえて誇張し、「主人公 or DIE」という極端な選別の論理を反復させる。この構図は、「勝たなければ存在しない」かのような社会的プレッシャーと、「勝利のその先に潜む空虚さ」とを同時に突きつけてくる。
本稿がこの曲をいま取り上げる理由は明確である。2020 年代半ばの日本社会では、SNS の可視化競争と生成 AI の普及によって、自分自身を“物語化”し続けることが当たり前の行動様式となった。だがその“自我脚本”が肥大化しすぎたとき、ヒーローの物語は容易に反転し、別の役割を帯び始める。『超主人公』に登場する「君」は、称賛を渇望するあまり周囲との関係に抑圧的な言動を見せるようになる。こうして「主人公」像が過剰に拡大されていく過程で、知らぬ間に別の立場――かつての対立者的な存在――へと変貌してしまうさまが描かれていく。
この作品を読み解くにあたり、本稿では筆者独自の三つの批評概念を用いる。それは「他者のリスク化」「アフター系」「ネガティブ・ケイパビリティ欲望」である。
- 他者のリスク化
2010 年代後半以降、炎上や誤情報の拡散、突発的なトラブルの増加によって、他者との関係性が「癒し」ではなく「損傷リスク」として知覚される傾向を指す。 - アフター系
2020 年代に現れた物語の潮流で、喪失や終焉を前提としたうえで、“何かのあと”の世界で生きる姿勢を描く。『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』や『葬送のフリーレン』などがこの系譜に属する。 - ネガティブ・ケイパビリティ欲望
解決不能や曖昧さに価値を見出し、それに耐えることを重んじる態度。すぐに答えを出すことをよしとせず、「分からなさ」を抱え込む力を称揚する。
これらの概念は、「傷つくことを恐れて距離を取りつつ、壊れた物語の余韻に耳を澄ませ、未解決の揺らぎを受け入れる」という一つの連続的な感性を形づくっている。『超主人公』は、そのような現代的感性に対し、ある種の警鐘とユーモアをもって問いかけているように思える。過剰な“主人公願望”は、やがて周囲との関係を圧迫し、自己の内面さえも脅かす。その姿は、私たちがしばしば無意識に演じている「ヒーロー像」への静かな批判として耳に残る。
II. 本論――ヒーロー神話の残骸を歩く身体は、なおも“いいよ”と呟く
LV あげすぎてスライムの気持ちがわからなくなる──この一節から、語り手の成長曲線はすでに飽和している。RPG の基礎敵キャラとの「差」が広がりすぎた結果、成長物語そのものが終わってしまったのだ。ここで作動するのが〈アフター系〉である。すなわち、レベルカンストというクライマックスを経てもスクリーンを閉じられず、経験値バーのない旅を続けてしまう奇妙な運動だ。標的も報酬も失われ、「World is mine」と叫んでも自己像は膨張して視界からはみ出す。ヒーローはついに、手にした「すべて」の使い道を見失い、空虚を埋めるためにさらなる称賛へ手を伸ばす。
だが称賛の供給源、すなわち他者は同時に裂傷をもたらす。SNS が火種となった 2010 年代後半以降、喝采はいつでも炎上へ転じ得る不安定なエネルギーになった。ここで顕れるのが〈他者のリスク化〉である。「邪魔するモブは排除したい」という心情は、傷つけられる前に傷つけたいという予防的暴力の欲望だろう。ヒーローは輝きを保つために群衆を必要とするが、群衆は容易に賞賛を撤回し「悪役」認定へと反転する。その二重の不安が「君に怯える子羊がいっぱい」という倒錯を生む。ヒーロー崇拝はそのままヒーロー恐怖症へとスライドし、喝采とおびえが交互に回転する。
さらに楽曲は「いいよ いいよ」と肯定を連打する。これは無条件の承認に見えつつ、実際には諦念の相槌である。ヒーローの自慢も危うい行動も「どうせ止められない」という無力感の中で消費される。まさしく〈他者のリスク化〉下の関係性──放置こそ最適な防御という冷笑的距離感だ。
ところが終盤、物語はもう一段ひねられる。「世界を滅ぼしたって?」という唐突な断末魔が示すのは、善悪の計器が振り切れて測定不能になった世界である。ラスボス化したヒーローは「次の主人公に倒されてバイバイ」と自己消滅の予言を口にする。ここで芽吹くのが〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉という私たちが静かに欲しているものだ。ヒーロー/ラスボス/モブの序列は永久に揺れ動き、誰も王座に固定されない。その不安定さこそ次のゲームを起動させ、聴き手はエンドロールを求めずループする不確定性を甘受する術を学ぶ。曲末の「君も次のラスボスじゃないかい?」は、聴き手すら無限の席替えゲームに巻き込む誘惑と警告である。
かくして『超主人公』は、〈他者のリスク化〉が招く予防暴力、〈アフター系〉が抱える終幕後の漂流、〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉が希求する未決着の姿勢──これら三層を有機的に重ね合わせ、ヒロイズムという神話装置の廃墟を音響で歩かせる。その掛け声は勝利の雄叫びではなく、余震のような揺れにすぎず、観客である私たちは崩れた足場の上で身をかわしながら踊る生存者にすぎない。
III. 結論――“ラスボスなき時代”を生き延びる物語の余白へ
『超主人公』が照らし出すのは、頂点に到達してなお終わらない競争のむなしさだ。輝かしいハイライトの裏側では、静かな崩壊が進み、喝采と痛みが同じテンポで跳ね返る。その光景は、スクロールを止められずに自己を誇張し、失速への恐れを隠すため言葉を過剰に盛る――そんな私たち自身の姿と重なり合う。
では、この先どこへ向かうのか。ヒーロー神話がラスボス化を繰り返す無限ループから抜け出すため、私たちはただ競争を降りるのか。それとも瓦礫の上で小さな火を囲み、かすかな営みを継ぐのか。答えは示されない。ただ〈いいよ〉と空しく繰り返す承認を手放し、「わからなさを抱えたまま立ち止まる力=ネガティブ・ケイパビリティ」を練習することが、唯一の出口になるかもしれない。おそらく、その練習風景こそが“次の物語”のプロローグだ。主人公かモブかを競うのではなく、序列のない場所で肩を並べる名もなき時間。そこではヒーローもラスボスも役割札を剥がされ、ただの人間として震えを分かち合うだろう。
『超主人公』が残した轟音の余白には、そんなささやかな連帯の種子がまだ蒔かれている。あとは――スクロールを止め、夜更けのモニターに映る「主人公 or DIE」の選択肢をそっと閉じる勇気を持てるかどうか。その瞬間、ヒーロー神話の残骸の下から、新しい物語の芽が静かに顔を出すはずだ。
※本記事は、ピノキオピー「超主人公」の歌詞を批評目的で最小限引用しています。著作権は作者および関係各社に帰属します。

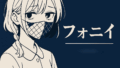
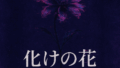
コメント