導入──ガチャの地層で息をする私たちへ
「バッドランドに生まれた/だけでバッドライフがデフォとか」
2023年末に公開された吉田夜世のボカロ曲 『オーバーライド』 は、開幕早々に〈ガチャ〉のメタファーを突き立てる。親の経済力、国籍、身体性——生まれながらに割り振られる初期値が、20年代の日本では“運試し”の軽薄な語で語られるようになった。「親ガチャ」「国ガチャ」。生得的差異は努力論を凌駕し、冷笑の通貨へ変貌した。本稿は、そうした偶然の暴力を受け止めつつも「上書き(override)」を試みる楽曲を、以下の三部構成で読み解く。
- 他者のリスク化——冷笑が防護壁になる社会心理
- 代理技術——記号化されたコミュニケーションの不協和
- アフター系——「終わったあと」を生き延びる物語倫理
ここで用いる三概念は、筆者による独自の整理である。それぞれの定義と時代背景を節頭で示しつつ、歌詞・サウンド・語りの構造を順にたどる。
本論──冷笑・代理技術・アフター系が織り成す一枚絵
『オーバーライド』は、一見するとバラバラな社会現象を接合したコラージュのように響く。しかし、その基底には他者のリスク化 → 代理技術 → アフター系という連鎖が脈打っている。
1. 冷笑という防護壁――他者のリスク化
まず、〈(笑)〉による予防線が張りめぐらされる。90年代以降、対人関係は「傷つく前に切る」前提で最適化され、ガチャという偶然の格差を指さしながら共感を回避する。曲中の〈巻き返しに必要な力で/別の事頑張ればいいじゃん(笑)〉はその象徴だ。笑い記号の刃が、リスナーを“分断済み”の世界へ案内する。
2. “コード化”する自己――代理技術
冷笑で薄まった人間関係は、SNS やボカロ音声といった媒介を通じて再配線される。〈アンタが書いた杜撰なコード/ばっか持てはやすユーザーよ〉が告げるように、ツイートやプロフィールといったメタデータ化した人格が流通の主役となる。ここでは「裏を読む」体験が仕様外であり、感情はピクセル単位に解像度を落とされる。肉声が削ぎ落とされたボカロの響き自体が、その冷たさを音響で可視化している。
3. 壊れたまま続ける倫理――アフター系
冷笑と代理技術によって“安全”が担保された世界は、その実、エンディング不在の閉塞を孕む。〈だけど最後、逆転の一手だけ/何故か詰められないの!〉という悲鳴が示す通り、ハッピーエンドを前提とする物語構造が瓦解している。にもかかわらず、主人公は動作を止めれば物語も途絶えるという恐怖から、エラーを抱えたまま再試行を選ぶ。これは『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』や『葬送のフリーレン』と同型の“余白を歩き続ける作法”であり、筆者がいうアフター系の倫理にほかならない。
4. 連鎖の帰結——聴き手へ委ねられる再生ボタン 他者をリスクとして避け、代理技術に感情処理を委ね、結果としてエンディングを失った――この連鎖の最後に置かれるのが、唐突なフェードアウトだ。曲はそこで終わらず、「再生/停止」の選択肢を聴き手に明け渡す。システムの次回起動権がクリエイターではなくユーザーの手へ移ることで、物語は初めて呼吸を取り戻す。冷笑も代理技術もアフター系も、最終的には“あなたの指先”を媒介に閉じるのだ。
結論──エラーを抱えたまま再生するあなたへ
『オーバーライド』は、
- 他者への冷笑という鎧をまとい、
- 代理技術に感情の手続きを外注し、
- アフター系の視座で失敗を抱きしめる——、
そんな主体が放つ“割り切れなさ”の闘争記である。override コマンドは作中で一度も成功しない。それでも再起動は幾度も試みられる。「直せないなら動かさない」ではなく、「直らないまま動かす」。この逆説的な粘りが、20年代を生きる私たちの呼吸法として提案されている。
最後に二つの問いを残そう。
- あなたは自身の〈半端な生命の関数〉を、どの行から**上書き(override)**しようとするのか?
- その上書きがまたバグを生むとして——再生を続ける勇気は、まだ残っているだろうか?
ガチャで配られた“荒地”は、あなたのスマホ画面の向こう側で静かに待ちつづけている。再生をタップして歩みを続けるのか、停止を押して立ち止まるのか──その選択肢は、この瞬間もあなたの手のひらに委ねられている。

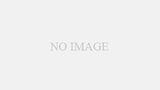
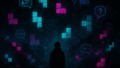
コメント