こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 歌詞の「すぐ」の意味に違和感を覚える人
- 本曲が現代のネット社会を歌っている予感がある人
導入――「一手遅れ」で暴かれるわたしたちの輪郭
2024年11月、柊マグネタイトが投稿したボカロ曲『テトリス』は、今もコメントを積み上げ続けている。本稿では再生数やランキングではなく、歌詞が照射する “暴露の瞬間速度” に焦点を当てたい。
「どうして “すぐ” 知ってしまうのか」——曲中で執拗に反復される “すぐ” という副詞は、プライベートな感情がネットへ漏れ出す潜伏時間がほぼゼロになった時代状況を示唆する。気づけば「もう言ってしまった」「もう壊れてしまった」──テトリミノが瞬時に底へ落ちるように、私たちの言葉や感情もセーブの余地なくタイムラインへ叩きつけられる。
本稿は以下二つの概念をレンズに読み解く。
- 他者のリスク化 ── 他者との接触が「喜び」より「損傷の危険」として先に知覚される傾向(2010年代後半〜)。
- ネガティブ・ケイパビリティ欲望 ── “わからなさ” や“不確定”を抱え続ける態度を希求する志向(2020年代半ば〜)。
『テトリス』ではネット社会におけるリスクと欲望の交差点が描かれる。どういうことか、さっそくみていこう。
本論――ブロックが落ちるたび、タイムラインに走るヒビ
まず冒頭の 「共振で…罵倒」 という断片に注目しよう。これは、誰かの失態に共鳴して赤面した直後、嘲笑へ転じる瞬間を切り出す。「同情 ⇒ 同調 ⇒ 罵倒」 の完了が、ネット社会の炎上回避の距離取りを表す。ここで作動するのが 他者のリスク化 だ。タイムライン上のアイコンは救済でも共感でもなく、さながらカド立つブロックとして並び、コメント欄は下から押し上げる消えないテトリミノさながらに失言を押し上げていく。
中盤で響く 「近未来しか勝たん」 というキャッチもネット社会の暗喩だろう。欲望と情報が等価に陳列された“モール型インターフェース”を示唆する。商品リンクも推しの切り抜きも同一棚に並び、私たちは“客”として歩き回る。ここで機能する 代理技術——匿名アカウントやアバター——は本来ユーザーの傷を肩代わりする盾だが、実際には痛みを拡散し娯楽へ変換する刃へ転じる。
弱音を吐く配信者に対し、チャット欄には 「送信で苦しい…草」 が滝のように降る。SOS が嘲笑へ置換される所要時間はスクロール幅と同じ。代理が受け止めるはずの火傷は、「大袈裟だな」という視線付きで本人へ返送される。2019 年以降の 「配信者叩き」や「晒し文化」 に重なる炎上構造だ。
後半において語りては「鬱とか躁とか…眠れない」とつぶやく。味方だとおもっていた帰属先を失い、自己破壊へ傾く切迫感を示す。ネット社会ではいつでも見ることが風景だ。そのようななか語り手は〈タタラタラ〉〈パパラパラ〉というオノマトペで不安を回転させ、列を整えきれなくとも落下軌道をわずかにズラす。あるいは回転し続けることで、消えることも、次のテトリミノの落下を防ぐことができる。
だからこそ「恥ずかしい過去…記憶消させて」 という訴えには切実なものが滲む。SNSでタグ付けされた履歴を解除したい衝動だ。しかしタグを外せば、キャラクターを抹消してしまえば、ネットでは存在ごと消えかねない。これは「恋人」「友人」といった既存ラベルで括れない 透明な関係 のジレンマを映す。ラベルを剥がせず震える声が、ラストの 「助けて/許して」 というエコーへ収束する。
結論――列がそろわなくても、落下音は止められない
『テトリス』が映し出すのは、
- 他者を怖れつつ、それでも声を上げざるを得ない “配信時代” の主体
- “答えの出なさ” に耐える筋力を渇望する 2020 年代の欲望
の二重写しである。
ブロックは今日も落下を続ける。危険を察知した瞬間、思わず 「キャンセル」 と叫びたくなるが、入力遅延のわずかなズレでその宣言は広場にさらされ、草の絨毯 に埋もれる。それでもゲームは止まらない。静かに距離を置く選択さえ「逃げ」とタグ付けされ、むしろ次の炎上の燃料に数え上げられてしまうからだ。
では “新しい列消し” は存在するのか。今のところ、曲は具体的な解法を示さない。提示されるのは 一手遅れで失敗を抱え込む身体の重み と、空白を空白のまま吸い込むリズム にほかならない。テトリスに “完全クリア” がないように、SNS のタイムラインにも決定的な終着点は存在しない。処理しきれなかった投稿や感情を積み残したまま、私たちは次々と流れる話題へ視線を移していくしかないのだ。
※本記事は、楽曲に対する批評的・文化的な考察を目的として、歌詞の一部を最小限に引用しています。著作権はすべて原作者・著作権者に帰属します。

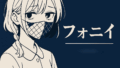
コメント