こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 本曲で描かれている関係性が知りたい人
- この曲の繋がりに尊さを感じ、それを言語化したい人
Ⅰ. 導入 ―― 正しさではなく、壊れないための祈りとして
ぬゆりによる楽曲『ロウワー』は、壊れてしまいそうな関係の中で、どうにか繋がりを保とうとする心の動きを描いている。語り手は「君と泣く 君と笑う」という繰り返しのなかで、離れそうになる不安と、繋がっていたいという願いのあいだを行き来する。だがその願いは、確かな論理や信念に裏打ちされたものではない。ただ、感情が壊れてしまわないように――そんな切実さから発されている。
冒頭の「そう簡単な祈りだった」という一文は、願いがもはや祈りとしてしか立ち上がらないほどに、言葉を失っている状態を示している。つまりこの曲で語られるのは、何かを証明するための言葉ではなく、「せめて今だけは耐えられるように」と祈るような気持ちで繋ぎ止めようとする感情そのものだ。
「段々と消える感嘆」「胸の中が澱のように濁る」といったフレーズからは、自分の気持ちがうまく言葉にならないまま積もり、やがて曖昧な不安や罪悪感として蓄積していく過程が読み取れる。語り手は「本当はこうしたかった」という思いを飲み込み、傷つけないために、あるいは壊さないために沈黙する。そしてそれは、相手を思う気持ちであると同時に、自分を守るための選択でもある。
本稿では、『ロウワー』に描かれたこうした感情の揺れを軸に、語り手が何を抱え、何を恐れ、何に救いを求めているのかを丁寧に読み解いていく。これは「正しさ」をめぐる物語ではない。関係が崩れそうなときに、それでもどうにか「まだここにいて」と願ってしまう心の、静かな記録である。
もし読者が、本曲になぜか惹かれているのであれば、ぜひこの記事を読んでほしい。その胸の内を共に言葉にし、確かなものにしていければと願う。
Ⅱ. 本論 ―― 離れることと繋がることの倫理構造
気楽な関係とは別の在りようで。
まず一つ、大きな謎を置いておこう。
『ロウワー』という曲において「繋がる」というのは何なのか。
現代を生きる私たちにとって「繋がる」という言葉や行為は非常にポップなものだ。スマホの画面からタップ一つで、あらゆる人や関係性、情報にアクセスができる。しかし本曲で描かれている繋がりは当然のことながら、そのようなカジュアルなものとは一線を画す。
『ロウワー』の語り手は、相手に対して何かを伝えたいという気持ちを抱えながらも、その多くを口にすることなく飲み込んでいる。「言いかけていた事が一つ消えてまた増えて」という一節は、感情が言語化されないまま蓄積されていく様を静かに描いている。語りたいのに語れない、わかってほしいのにわかってもらえる自信がない――そうした未処理の感情は、関係のなかに澱のように沈殿していく。
さらに「従いたい心根を吐き出さぬように込めて」という表現が示すのは、言葉にすることで相手に委ねてしまいそうな本心を、必死に胸の内に留めておこうとする態度である。ここで重要なのは、語り手がただ自己抑制をしているのではないという点だ。これは、自分の気持ちをぶつけることで相手を困らせたり、関係を壊してしまうことへの恐れでもある。つまり語り手は、語らないという選択によって相手を守ろうとし、その結果、自分の内面が「濁る」ことを受け入れている。
これだけでも『ロウワー』の繋がりが決してカジュアルなものではないことがわかるだろう。
では、この繋がりは具体的にどのようなものなのだろうか。
しかし残念ながら、この関係は言葉にできないのだ。本曲が「まだ誰も知らない感覚」と謳っているように。だが、この感覚のヒントはある。それがこの曲の通奏低音でもある、「壊れる」予感である。
繋がることが、同時に「壊れる」予感を呼び寄せる
確認したいことがある。『ロウワー』において「繋がる」という行為は、決して無邪気な希望ではないということを。
語り手は「その度に何回も繋がれるように」と願うが、それは裏返せば、「繋がりは途切れるものだ」という前提を含んでいる。
しかし、である。
『ロウワー』の語り手は、繋がることをただ一度の奇跡とは捉えていない。むしろそれは、繰り返し断絶し、繰り返し再接続を祈り続ける行為として描かれている。
「その度に何回も逃げ出せるように」
「心が守れるように 奪われないように」
という一連のフレーズは、関係を続けるためには逃げ道も必要だという認識を示している。
これは、「本当の絆なら壊れない」という安易な信頼とは対極にある。むしろ語り手は、絆が壊れる可能性をつねに見つめながら、その現実に備え、同時にそれでも繋がっていたいという願いを手放さない。その繊細な態度は、表面だけ見れば臆病にも思えるが、裏を返せば、相手を不当に縛らないための優しさでもある。
ここで敢えて言おう。この曲の繋がりは、どのようなものなのか。
語り手は、相手を「わかってくれる人」ではなく、「わからないままでも関わってくれる人」として信じようとしている。その信頼は理想や幻想ではなく、むしろ不安と疲れの末にようやく選び取られた、切実で現実的なものなのだ。
振り返って考えてみてほしい。この関係は、一朝一夕で築けるものではない。私たちが生きる現代は、自らが思っている以上に自由である。気に食わなかったら離れればいい。趣味が近いコミュニティには親しくなるという確信にも似たものがあるから飛び込める。
故に「わからないままでも」という前提は、現代において稀有なものであるといえるのではないだろうか。そして更に、それでも、関係の中に留まろうとしてくれることは奇跡に近い。
人は変わる。心も変わる。月日が経てば立場も違ってくるだろう。それ故に離れることもあるだろう。
だが、それでも関係のなかに留まってくれる。それはなぜか。恐らく、語り手も、相手もお互いの始まりのときを知っているのだ。
君が何者でもなかった頃、自分が何が得意で何が不得手なのかすらわからなかった頃、そんな原初の頃を知っているのだ。小学生の頃でもいい、中学生の頃でもいい。もっとずっと過去のことでもいい。何者でもなかった頃の自分を「君」は知っているのだ。
それは、言いたいことを言い合う関係ではない。胸の中が澱のように濁っても、言うべきことを言ってくれる関係だ。言うべきことがわからなくても、その戸惑いを誤魔化さない関係だ。
だからだろう。「そんなことを言っても、お前だって最初は」と言ってくれる存在を私は思い出す。いや、私だけではないはずだ。
そして、こんなことを「これから何度思い出すだろう」か。その答えは、まだ、わからない。
Ⅲ. 結論 ―― 感情が擦り切れる前に、君を知ろうとして
語り手は強くない。むしろ、その弱さゆえに、優しくなろうとする。語らずにいることで相手を守り、逃げ道を用意することで関係を支える。
「僕らが離れるなら 僕らが迷うなら」
という反復に込められたのは、「壊れないこと」を信じきれない現実のなかで、それでも繋がろうとする意志だ。他者との関係が、ただの情緒的な癒しではなく、「自分が生きてきた」という実感そのものに結びついているという切実さが滲んでいる。
この歌は、誰かに強く想われたいという衝動の歌ではない。むしろ、自分の感情がすり減ろうが、せめて君に触れておきたい、君と何かを交わしておきたい――そのような静かな切実さが通底している。関係を「築く」のではなく、「崩れないように支える」ことに注がれる祈り。それが、この曲の核である。
だからこそ『ロウワー』は、多くの人にとって、何かを語りたくても語れなかった夜、あるいは繋がっていたはずの誰かを思い出す瞬間に、そっと寄り添ってくる。これは、一つの答えではなく、答えを持てなかった人たちが交わした「それでも生きていこう」とする声の記録なのだ。
※本記事は、楽曲の評論・批評を目的として歌詞を一部引用・参照しています。著作権はすべて権利者に帰属します。

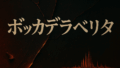

コメント