こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 本曲を通じてボーカロイド曲の歴史を知りたい人
- 「ヴァンパイア」という言葉に込められた意味を知りたい人
導入――「愛してほしい」は、どうしてこんなにも醜く響くのか
「吸っちゃっていいの?」と問う声が、切実で、哀しくて、少し笑える。DECO*27『ヴァンパイア』の語り手は、他者との境界を越えたいと願いながら、その願いが軽蔑や嫌悪の対象となることを、よく知っている。だからこそ、ヴァンパイアを自称するのだ。
ところで、この曲に惹かれる者はきっと、愛されることを望んでいる。しかし、それが不格好だという自覚がある。だが、いや、だからこそ、自分の内側のコントロールできないような感情や執着を、語り手の姿に重ねてしまうのだ。
本稿では、『ヴァンパイア』の歌詞を構造的・情動的に読み解きながら、この語り手が抱える矛盾と、それに共鳴してしまう私たちの実感との交差点を探ってゆく。語られた欲望のかたちを通して、なぜ私たちは“吸いたい”のか、なぜ“吸われたい”のか、その答えにならない問いに、そっと触れてみたい。
まずは、冒頭から示される命題「ヴァンパイア」を自称することの意義を考えてみたい。
構造分析――ヴァンパイアという自己規定の謎
冒頭のヴァンパイアという自己規定は、単なるキャラ付けではない。他者を必要とする存在としての自己肯定であると同時に、その依存性への羞恥ではないだろうか。それ故に本曲は、いびつな構造を取る。
サビとAメロの関係を見ると、Aメロでは「不安」「たられば」「要らないだけ」など否定的な語彙が目立つ。これは「愛されたい」という欲望が前景化するサビと強い対比をなす。感情は常に行き来し、
「最低最高 ずっといき来してる」
というフレーズそのままに、肯定と否定、期待と絶望の間を振り子のように揺れている。
しかし、この懊悩は「ヴァンパイア」という自己規定によって、キャラ付けされるのだ。だが、素朴な疑問として、なぜこのような規定が必要なのか、と考える必要がある。先程「他者を必要とする存在としての自己肯定であると同時に、その依存性への羞恥」と書いたものの、それはヴァンパイアというキャラ付けに対する必然にはならない。むしろラヴソングの類であれば、そのような苦悶は曲のスパイスとなりうる。
そうだとすれば、ヴァンパイアというキャラの意味は、それが人間社会の通念への挑戦という風に考えることはできないだろうか。例えば、不倫や浮気の類。そのように考えれば、ヴァンパイアという夜にしか動けないキャラという自己規定の必然性が浮かび上がるのだ。
本曲が非常にポップでかわいらしいものであるから、わかりにくいかもしれないが、歌詞だけを読みこむとそのような可能性が見えてくる。だからこそ、本曲の最後は「きみもヴァンパイア」という展開を迎えるのだ。
社会状況との照合――ボーカロイドの挑戦
ここでは、あくまで「不倫や浮気」というものだけを取り上げたが、ここまで読んでくれた読者には、本曲の自己規定の必然性が、前述だけのものではないというのがわかると思う。特に「多様性」が至るところで主張されている現代であれば、直観的にわかってくれると信じている。
ただ、考えてみれば、ボーカロイドというサブカルチャーは、社会通念に対する不断の挑戦でもあった。詳細は、鮎川ぱて『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』という本に譲るが、ボーカロイドには、アンチ・ラブソングやアンチ・フィジカルなどを題材とした曲が数多存在する。本曲は、そんな伝統の延長線上にあるのだろう。
これが筆者の独りよがりな考えではないことは歌詞そのものが証左となるだろう。
「「正に」ばかり/割り切れないけど余りじゃない」
一見じれったい恋心の比喩のようにみえるが、その内実は、何よりも切実な思いであることは、もはや言うまでもないだろう。
結論――愛してくれなくていいから、嫌いにしないでほしい
『ヴァンパイア』の語り手は、誰にも届かない場所で渇き続けている。その渇きは、愛されたいという願いのかたちをしているが、ほんとうはもっと曖昧で、真剣で、もっと重々しい何かだ。
この歌詞に共鳴する人はきっと、誰かに「欲しい」と伝えることが怖いのだろうと想像ができる。それでも、怖がってばかりではもういられない。誰にも言えなかった渇望を、ポップなリズムに乗せて叫んでくれるこの曲は、そうした“言えなさ”を抱えた人々の心に、まるで代弁者のように寄り添う。
語り手は何度も「絶対いけるよ」と繰り返す。それは他者に向けた肯定ではなく、自分を無理やり納得させる呪文のようにも聞こえる。だが、その繰り返しのなかにこそ、聞き手は自分の影を見る。
傷つけてしまうかもしれない。崩れてしまうかもしれない。
それでもなお、つながりを求める曲の強さは、勇敢という言葉以外の形容がみつからない。
この曲はきっと、そんなあなたの弱さに、最初から味方している。
※本記事は、楽曲の評論・批評を目的として歌詞を一部引用・参照しています。著作権はすべて権利者に帰属します。


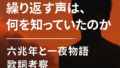
コメント