こんな人におすすめの歌詞と考察!
- この曲に描かれている「承認」の仕組みを知りたい人
- 曲中の毒や鏡のモチーフの意味が気になる人
導入|「好き」と言いながら、「生きていたい」と願うということ
『レビテト』という楽曲は、感情の高まりを露骨に示すことのない歌である。むしろ語り手は、どこまでも醒めていて冷静だ。毒を吐きながら、鏡を覗き、数値を見つめて、静かに「好き」と言う。だがその「好き」は他者に向けた感情ではない。鏡の向こうの自己に対して──あるいは自己の残像に対して──つぶやかれる言葉だ。そしてその「生きている」という実感もまた、幻想のなかでさえも自分を見失わずに済んだことへの、ぎりぎりの祈りなのだ。
この語り手は、「私だけを愛して」などとは言わない。作中でそれを明確に否定することで、あたかも愛を求めていないかのような姿勢を見せる。だが、この否認こそが、逆説的にその飢えの存在を証明してしまっている。語られる「幻想」は、過去に受けられなかった承認と、未来に期待してしまう承認とのあいだに宙づりになった痛みの痕跡である。
作中に登場するモチーフ──鏡、毒、幻想、数字──はいずれも、語り手が自らのアイデンティティを保ち続けるための媒介物だ。誰かに愛されたい、必要とされたいという衝動を、露骨に発することができない者が、自傷に近い方法でそれを示す。その姿は、SNS上の「いいね」やフォロワー数といった“数値的な確かさ”にしがみついて、自己の輪郭をかろうじて保とうとする私たちの姿とも重なって見える。
『レビテト』は、承認を求めることにさえ疲れ果てた誰かが、それでもなお「私はここにいる」と言いたいときに選ぶ歌だ。肯定や救済ではなく、淡々とした不満と冷笑のなかで、わずかに芽吹く自己肯定。そのかすかな震えこそが、この歌のいちばん大事なところにある。
本論①|承認への飢えと「毒」の戦略性
『レビテト』の語り手は、他者からの承認を欲していないふりをしながら、その欠如を繰り返し訴えている。序盤では、「なんでも自分ばかりが損をしている」と感じている様子が描かれ、さらに「世界のなかで浮いているようだ」という自己認識へとつながっていく。けれども、それを「寂しい」「つらい」とは素直に言えない。そのかわりに彼女が選び取るのが、“毒”という戦略である。
語り手は、感情を正面から出すことなく、すねたように冷笑的な言葉を吐く。その語り方には、あからさまな攻撃性というよりも、愛情の裏返しとしての屈折や拗ねが含まれている。他者に好かれないこと、理解されないことをすでに織り込んだうえで、しかしそれでもなおどこかで関心を惹きたいという欲望が、語り手の言葉の端々からにじみ出ている。
この「毒」は、自己防衛であると同時に、承認を引き寄せるための“裏ルート”として機能している。つまり、「良い子」でいることを諦めた自分をさらけ出すことで、正面からの愛ではなく、同情や注目、あるいは共感といったかたちの疑似的な承認を得ようとするのだ。これは、自己評価の低い人間にしばしば見られる防衛機制であり、「どうせ私なんて」と語りながら、「それでも誰かに気にかけてほしい」と願ってしまう、きわめて人間的な屈託である。
しかも彼女は、その屈託の存在をある程度自覚している。「少しだけなら見せてもいい」と語るくだりでは、弱さや毒が“他人の視線”によって価値を帯びていくという構図が浮かび上がる。彼女は、自分の内面が見られることをどこかで欲しながら、それを否定する演技もまたやめられないのだ。毒のなかに自己を宿らせることでしか、自分を維持できないという選択。それがこの語り手の姿である。
承認されたいけれど、される自信はない。その矛盾を解決するために、彼女は「わかりやすく好かれる」ことをあきらめ、「嫌われすぎない程度に毒を吐く」という選択をする。これは単なる拗ねではない。承認への複雑な戦略であり、同時に、存在を保ち続けるためのぎりぎりの自己保存なのである。
本論②|数字が与える実存的確証とその脆さ
『レビテト』の語り手が最終的に頼るのは、人ではなく「数字」である。曲の終盤、《暗い暗い部屋の隅で見てた/ただ確かな数字が/居てもいいと言うの》というフレーズが象徴的だ。これは、SNS的な承認システム──「いいね」や再生回数、フォロワー数といった可視化された他者の関心──を通じて、自分の存在が保証される感覚を描いている。
人は不確かである。他者の愛情は変わるし、承認は気まぐれだ。しかし数字は──少なくとも語り手にとっては──「確か」である。誰かが一度押した「いいね」は、取消されない限り、そこに残り続ける。数字は語り手にとって、変わりゆく世界における唯一の可視的な“根”となる。
だが、その「確かさ」はあくまでも量的な慰めに過ぎない。誰が押したか、なぜ押したかはわからない。匿名の、文脈を持たない関心。それでも語り手はそこに意味を見出そうとする。なぜなら、自分が“存在してよい”という言葉を、誰かの口から直接聞くことがなかったからだ。数値が承認の代替物になったのではなく、数値しか承認の回路が残されていなかったのである。
ここで「鏡」が果たす役割も大きい。《好き/鏡越しでも/好き》というラインにおいて、彼女は直接的な対人関係ではなく、「自己像の中の自己」と向き合っている。つまり、それは数値的・量的なもののために必死になっている自分も好きなのだ。
改めて整理しよう。彼女(語り手)は、まず第一に彼女は鬱屈している。それを自覚し、そのうえで「毒」を吐き出す。そして、それで得た承認に癒されるも、その癒しに酔っている自分すら自覚しているのだ。これは一つの牢獄である。彼女が最終的に癒られるのは自分自身によるものなのだ。自分で自分を慰める。それ以外の回路を知らない。具体的な他者の不在。だから、こう言える。このように繰り返せる。これは一つの牢獄なのだ。
結論|幻想でも、生きていたかった──欺瞞を引き受けるということ
『レビテト』における語り手の姿は、誤魔化しや欺瞞に満ちているように見えるかもしれない。「好き」と言いながら、本当に何を愛しているのかは曖昧なまま、「愛してほしい」とは言わず、「ただの幻想と知って未だにやって」いる──それは一見すれば、滑稽で、哀れで、あるいは自己矛盾の極致であるかもしれない。
しかし、その矛盾をこそ彼女は生きている。誰かに承認されたい、でも真正面から欲しがる勇気もなく、だから“毒”をまとって関心を引こうとする。そのくせに「数字」に安堵し、「鏡越しの自己」にしか愛を告げられない。これはまさに、現代における自己保存のリアルである。
現実と幻想のあいだで裂かれた彼女の姿は、「承認されないまま生きる」という状況のなかで、それでも「生きていたい」と願った者の倫理を映し出している。つまり、『レビテト』は「本物の感情」にたどり着けなかった者の敗北の歌ではない。それは、欺瞞を欺瞞として抱えたまま、それでも自分を生かし続けるための闘争の歌なのである。
語り手にとって、幻想は嘘ではない。それは仮構でありながら、彼女を生かす装置であり、数字や鏡や毒といった媒体は、その装置を駆動させる燃料である。もしもそれらすべてを「くだらない」と切り捨ててしまったなら、彼女はすでに「生きていない」。語り手は、そのことをよく知っている。だからこそ、リフレインする。《くだらないわ/だけど生きてると感じるの》と。
ここには、一見後ろ向きに見える「欺瞞の中での生存」がある。だがそれは、感情のリアルをあらゆる虚構で包み込みながらも、どうにか現実にしがみつこうとする──現代的な感情のかたちである。その姿に自らを重ねるとき、私たちは彼女のように、小さな毒を抱えたまま、確かな数字や歪んだ鏡に救われながら、今日を生きているのかもしれない。
※本記事は、楽曲の評論・批評を目的として歌詞を一部引用・参照しています。著作権はすべて権利者に帰属します。


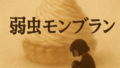
コメント