こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 「弱虫」の本当の意味を知りたい人
- 本曲に込められた皮肉な構造を知りたい人
【導入|「弱虫」のダブルミーニング】
DECO*27による楽曲『弱虫モンブラン』は、甘美なタイトルとは裏腹に、重く、苦い感情の残滓を語り続ける一曲だ。恋愛の終わり――あるいは、その最中に訪れる“終わったような気配”を描きながら、この曲の語り手は、自分自身の感情にすら確信を持てないまま言葉を綴っていく。
「“嘘であって”と願う」
この一節に象徴されるのは、“信じたい気持ち”と“信じられない現実”の間で裂けるような心の動きである。
この曲では、愛していたはずの相手を忘れかけている自分、けれどまだどこかで触れているような感覚が残る自分、そしてその矛盾に耐えられず「弱虫」と自嘲する自分――そうした複雑な層が重なっていく。つまり、語り手は「誰かを愛した」という経験すら、すでに自分の一部として抱えきれなくなっている。
ここで重要なのは、「感情の外在化」――すなわち、自分の中から湧き起こったはずの想いが、自分のものではないように感じられる状態である。これは心理学や哲学で「疎外」と呼ばれる概念に近い。他人との関係だけでなく、自分の感情や記憶すらも遠ざかってしまう感覚。この曲の語り手はまさにそのような“自分から遠くなる”苦しさの中にいる。
『弱虫モンブラン』は、感情が確かなものとして信じられなくなった時代に生きる私たちに、「じゃあ、それでも誰かを想うって、どういうこと?」と静かに問いかけてくる。そして、それは同時に「理性」というものの悲劇が滲む場面でもある。本曲を聞いた人のなかに、どれほどいるだろうか。
この「弱虫」という言葉が二重の意味になっていることに気づいたのは。
どういうことか。このことを歌詞の中から丁寧にみていきたい。
【本論①|感情の輪郭が溶けていく──「誰を愛していたのか」を忘れるということ】
まずは本曲の基本線から確認していこう。
『弱虫モンブラン』の歌詞は、恋愛の苦しみや別れの痛みを描いているようでいて、実際にはもっと根深い問題を扱っている。たとえばこの一節──
愛したのは誰だっけ?
これは単なる恋の記憶喪失ではない。問題は、「愛していた」という感情の実感すら曖昧になっていることだ。語り手は、過去に確かに何かを愛していたのだが、その相手も時間も、感情の重みすらも霧のように薄れていく。そして、「まだ触れてるハズなのに」と言いながらも、それを確かめる手段が見つからない。
こうした描写が訴えてくるのは「想い」が時間とともに自分の内側から流れ出ていくような感覚だ。愛した記憶が、もはや“自分のもの”とは言い切れない。それはまるで、かつて自分の中に確かにあった「誰かに触れたいという気持ち」が、いまでは外側に滑り落ちてしまったかのようだ。
こうした感覚は、先述した「疎外(そがい)」という心理状態に近い。疎外とは、自分の感情・身体・行動などが、自分から切り離されて他人のもののように感じられる状態である。たとえば「泣いているのに、なぜ自分が泣いているのかわからない」といった感覚が、それに当たる。
ここにあるのは「好きだったはずの感情が、自分の内部で手応えを失っていく」という不気味な経験である。自分のなかにあったはずの強い感情に留まることができない現実。これが彼女を「弱虫」にしていくのだ。
【本論②|“本当”という言葉にすがるしかない理由】
『弱虫モンブラン』で繰り返される言葉がある──それが「本当だって良い」というフレーズだ。
この言葉に込められた語り手の感情は、どこまでも矛盾している。「本当であってほしい」と願う一方で、「嘘であってほしい」とも願ってしまう。これは一見すると意味不明な二重性だが、実際にはとても切実な心理である。
ここで注目すべきは、語り手が自分の感情を“体験”することではなく、“判断”しようとしている点だ。「この想いは本当か、嘘か」「これは正しいのか、間違いなのか」。感情が流れるままに感じられるものではなく、正しさや意味を問い詰めなければ成立しないものになってしまっている。
この構造は、まさに「捏造された感情」という言葉で言い表すことができる。つまり、本来であれば自然に湧き起こるはずの気持ちを、語り手はあらためて「これは本物か?」と問い直し、そのつど自分の感情を組み直していく。それはまるで、自分の気持ちをパーツとして再構成する作業のようである。
ここにきて本曲のモチーフについて、ある可能性が浮かび上がってくる。
つまり歌詞の語り手は、弱虫という言葉が導くようなナイーブな存在ではなく、徹頭徹尾理性的な存在なのではないか、ということだ。
すぐに反論がありそうな推論である。なぜなら前節で「好きだったはずの感情が、自分の内部で手応えを失っていく」という感覚について議論したからだ。
しかし考えてみてほしい。強かった思いは時の流れと同時に減退していくというのは一見当たり前にみえるが、一方で心の傷になる可能性だってあるのだ。しかし後者の可能性を無視し、曲の語り手は感情の忘却を推し進める。
このような選択を目の当たりにしても、語り手をナイーブと称するのは、いささか無理筋な読みであると言わざるをえない。
【本論③|理性の悲劇
さて『弱虫モンブラン』の歌詞の中で、「コントラクト(契約)会議」という不思議な言い回しが挿入されている点に注目したい。通常、恋愛は“自然に始まるもの”という幻想のもとに語られることが多い。だが相手に「堕ちる」ことは、語り手は何かの契約のように、制度的に、避けられない流れとして受け入れている。
ここまでくれば、語り手が抱えてみたものが、もはや愛情ですらない可能性もみえてくる。
どこまでも、理性的で、選択的で、計算的な感情だろう。
だが曲中で一か所だけ、その理性が崩れそうな箇所がある。
「君が死ねばいいよ 今すぐに」
これは決して本気の呪詛ではない。むしろ、「自分がこれ以上、あなたに堕ちてしまわないように」という自己防衛の裏返しである。語り手にとって“あなた”は、自己崩壊の引き金でもある。だからこそ、それを断ち切る最後の手段として「死ねばいい」と言うしかない。
しかし、先の一言を語り手は繰り返したがっている。「もうアタシはキミに伝えられない」という言葉がその証左だろう。理性で始まり、理性で断ち切り、理性で終わらせた。本曲に流れている感情は、そのような通奏低音がある。語り手は「あなた」に堕ちたがっていたのだ。
ここにきて「弱虫」のもう一つの意味が現れる。
「堕ちる」ことを理性で断ち切ってしまった自分のことを本曲では「弱虫」と言っているのだ。
恋愛のような感情に留まることができなかった自分がいる一方で、理性によって強い感情に落ちることができなかった自分。
この二つが「弱虫」の本当の意味ではないだろうか。
【結論|“弱虫”であることの意義──揺れを引き受ける強さ】
『弱虫モンブラン』というタイトルは、当初は自嘲に近い響きを持っているように思える。感情を持て余し、自分の気持ちにすら確信を持てず、誰かを愛していたはずなのにその記憶も曖昧になる語り手は、自らを「弱い虫」と呼ぶ。その姿は、たしかに“情けなく”、未成熟に見えるかもしれない。
しかし、ここで描かれている「弱さ」は、単なる無力さではない。それはむしろ、自分の感情が偽物かもしれないと疑う痛みを受け止める誠実さであり、曖昧なままの関係性を断ち切れずにいる苦しさを誤魔化さない正直さでもある。
『弱虫モンブラン』は、恋愛という主題を借りながら、実際にはもっと深い問いを投げかけている。「自分の感情を、どこまで信じていいのか」という現代的な不安。それに正面から向き合うことは、決して弱さではない。むしろ、揺れ続けることを受け入れるという、ある種の強さである。
語り手が最後まで自分の感情に「本当」と言い切れなかったことは、敗北ではない。曖昧なままの痛みを、ちゃんと痛みとして見つめることができた――そのことこそが、彼女を“ただの弱虫”から救い出している。
だからこそ、この歌を聴いて心を動かされるあなたもまた、「自分の感情が信じられなくなる瞬間」を、どこかで知っている人なのかもしれない。そしてその不確かさは、他人を傷つけないための、あなたなりの優しさでもあるのだ。
※本記事は、楽曲の評論・批評を目的として歌詞を一部引用・参照しています。著作権はすべて権利者に帰属します。

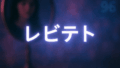
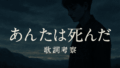
コメント