序論:新解釈『モザイクロール』
かつて援助交際がマスメディアで取り上げられ、社会問題化した時代に「魂が汚れる」と女子高生を咎めた評論家がいたそうだ。1990年前後の話である。
しかし逆をいえば、「魂が汚れる」という程度の言葉でしか、大人たちは子どもたちを非難できなかったのである。
それから数十年結果した現代においても、恐らく大人たちは、そんな子どもたちを叱るために有効な言葉を持っていない。「倫理」というものは、昔よりもずっと薄くもろくなっているのだ。
DECO*27『モザイクロール』という曲は、その壊れかけた「倫理」の向こう側を描いているように思える。多くの視聴者は、この曲を「終わりかけの恋」の歌だと思うだろう。しかし私は逆だ。ここに描かれている「あたし」と「きみ」の物語は始まってすらいないのだ。「倫理」なきところに礼儀正しい愛など存在しない。どういうことか。それをこれから本曲の歌詞を辿って、意味を吟味しながらみていこう。
一章:「始まってすらいない」という原点
まず前提として、この曲が「終わりかけの恋」だと思われる点をみていこう。端的に表しているのが曲中の「思いやりの欠如」や「形だけ」というフレーズだろう。そのうえ「腐れ縁」と続いているのだから「終わりかけ」という印象を視聴者に抱かせるのは自然なことだ。
しかし、問題はその前段にある。「傷口から漏れ出す液を“愛”と形容してみた」という点に注目したい。疑問に思うべきは「形容してみた」という表現だ。このフレーズを置くことで「愛」というのは、あくまで仮定の話になる。もしこれが「終わりかけの恋」の始まりだったのであれば「漏れ出す液は間違いなく愛だった」というふうに過去を回顧し、そのうえで断定してもいいはずだ。にもかかわらず「あたし」は断定を避ける。ここだけではない。「「愛した」って言うのですか?」というサビにも注目すべきだ。ここにも断定を避ける仕草が色濃く表れているのは、誰の目にも明らかだろう。
未試聴の読者にはぜひ一度本曲を聞いてほしい。いや、何度も聞いたことある人にも改めて聞いてもらうことを私は望む。この曲に登場する「愛」にまつわるフレーズには、仮定的であり、試験的なのだ。
では改めて、ここで歌われていることは何なのだろうか、ということを考えなくてはならない。
二章:「倫理」の荒野から始まる
最大のヒントは、この曲の冒頭にある。「とある言葉がきみに突き刺さり/傷口から漏れ出す液」というフレーズ。ここは単なる艶めかしい表現ではないというのが本論の読みである。まず「突き刺さり」という言葉に注目したい。この表現の前提には、保護膜のような何かで覆われものの存在を暗喩している。ここからは飛躍していることを承知でいうが、この保護膜こそ私たちが「倫理」と呼んでいるものではないだろうか。実態があるものではないということは「言葉が(…)突き刺さり」という点からもわかると思う。そうであるならば、この表現は生々しいものを表しているのではなく、非常に抽象的なものの言い換えではないだろうか。そして、その抽象的なものこそが「倫理」であり、漏れ出す液は「欲」なのだ。
「あたし」と「きみ」の関係性は、そんな倫理が突き破られたところからはじまっている。故に次のフレーズは自然なものなのだろう。「愛か欲か分からず放つことは何としようか」がそれである。
ここからは想像だが、そのような場所から始まった二人の関係性は、その誕生の瞬間から終わることが決定づけられていたのだろう。いわゆる「カップル」や「付き合っている」といえるような健全な関係性に、この二人は戻れない。なぜならこの二人は「倫理」を飛び越えてしまう、ということをお互いに知ってしまっているからだ。そこに宿るのは信頼ではなく、不信である。どんな言葉も、会話も「そう思わせたいだけ」や「言い訳だ、嘘だ」という風に無限の後退してしまう。話し合いが成り立たないのだ。故に終わることは始まった瞬間から決定づけられていた。だからこそ、この曲は「これも運命じゃないか 消える消える」というフレーズで締めくくられる。
結論:今更「倫理」といわれても
いかがだっただろうか。本論が行った『モザイクロール』の解釈については、もちろん納得できない人もいるだろう。だが、「一理ある」と一瞬でも思ってくれたのであれば望外の喜びだ。
ただ、考えてみれば『モザイクロール』という曲名すら本論の解釈を補強していると思えなくはない。「モザイク」の辞書的な意味は「映像や写真・画像の一部または全部をます目で区切り、消したい部分の区画をぼかして見えなくすること。また、その処理」である。そして「ロール」には「役割」「役目」という意味がある。
ぼかしたくなるような役割、見えなくするような加工を加えた役目というのがタイトルの直訳になるのだろう。そうであるならば、やはりここでいう「見えなくするような」場所というのは、繰り返し述べているように「倫理」の向こう側のことではないだろうか。
では「倫理」の脆さから生まれた関係性の曲が、なぜ数年前に歌われたのか。なぜ人気を博したのか。しかしながら、そのような疑問を読者が抱いたとしても本論では、現代的な状況と結び付けない。90年代からあらわになった「倫理」の脆さを語るには、あまりにも今更過ぎると思うからだ。

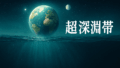
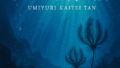
コメント