本論はDECO*27の『チェリーポップ』を扱う。とはいえ、本曲は子どもっぽい恋心を歌っているだけのかわいい楽曲のように思える。歌詞の内容についても、70年代から出現した「ポップス」と分類された曲たちが有していた機能しか有していないように聞こえるだろう。つまり「ニューミュージック」や「ロック」のように視聴者の実存に響くようなものではなく、場や気分の演出に有効な楽曲というわけである。
しかし、ここで考えてみたいのは、本曲に現れる「かわいい」の分析だ。例えば「ちねちねちね」や「おばか」という表現も、多くの視聴者には「かわいい」という印象を抱かせたに違いない。だが、本曲の子どもっぽい恋心は、なぜ「かわいい」という表現を経由しなければならなかったのだろうか。つまり、なぜ恋心に対して「かわいい」という加工をしなければならなかったのか。その恋心が本心であれば、なぜ「かわいい」を経由しなければならないのだろう。
結論からいえば、ここには「かわいい」という表現でしか伝わらない、とあるメッセージがあるのだ。それを本文で紐解いていきたいのである。
ロマンチックからキュートへ──主体なきコミュニケーションの発見
この問題を考えるうえで、一つ強力な前提を差し込まなくてはならないだろう。女の子たちは「かわいい」は何を指してきたのか。禅問答のような話だが、これに対する回答はある。社会学者・宮台真司『サブカルチャー神話解体』には次のような文章がある。
「ロマンチックな「かわいさ」が「自分と<世界>のロマン化」として自閉的・自足的なのに対して、キュートな「かわいさ」は、「これってあたしっぽい」といった自己意識においてのみではなく、外向きに奔放な、しかし軽くて傷つけ合うことのない対人関係の形成においてこそ、その力を発揮するのである」。
補足しよう。宮台が行っていることは「かわいい」が、どのような時代で、どのような特徴があり、それがどのような機能を有していたのか、ということの分析である。つまり、かつて「ロマンチック」な「かわいさ」は、あくまで自己満足的な、世界を「すばらしいもの」だとするようなフィルターとして機能していた。だが、その後に現れた「キュート」な「かわいさ」は、他者と傷つかないコミュニケーションを可能にした、というのだ。
「女の子たちは、「かわいいもの」が、主体なきコミュニケーションを可能にすることに気づいた。ここに対人関係の形式的なコードとしての「キュート」が発見された」
そして、更に次のように続ける。
「「本当の<私>」を詮索するのをやめにして、「みんな同じ」であることを巧妙に先取りしてしまうコミュニケーション。それこそが、キュートな「かわいさ」の、対人関係ツールとしての本質的な機能なのである」
「かわいい」は、それを使いこなしている限り、使い手や受け手を深く傷つけることはない。
しかし、である。
勘のいい読者であればわかるだろう。このような「かわいい」は、『チェリーポップ』で歌われているような、恋心の伝達を担わせるには非常に相性が悪い。
冗談としての恋心──傷つかないためのルール
『チェリーポップ』の語り手は、決して本気にならない。どんな本心にも常に一定のブレーキをかけている。例えば「愛していい感」や「恋していい感」というフレーズが、そのことを表す。誰かに許可を求めるわけでもない。かといって、自分の心を決めているわけでもないような「感」という一文字。
前述の「かわいい」の機能や、「感」からにじみ出る恋心に対する距離感からも、その裏には「安全」で「傷つかない」戯れを語り手が規定していることがわかる。たとえ恋愛のように「「本当の<私>」を求められるものでも、それをひた隠しにし、生じるであろう傷を極限まで抑えようとしているのだ。
すべて戯言。
すべて冗談。
すべて虚構。
それがたとえ、誰かを好きになるという気持ちであっても。
しかし、そもそもなぜ、そのようなスタンスでなければならないのだろうか。最初から「冗談」と言い訳ができるような恋心なら、伝わるものも伝わらないと感じてしまう。それこそ今風にいえば「タイパ」が悪いのではないか、とさえ思う。だが、ここで私たちがしなければならないのは、このような説教じみたことを考えることではなく、どのような価値観が、そのような「タイパ」の悪い恋を生じさせてしまうのか、ということだ。
ここからは想像ではあるが、このような「タイパ」の悪い恋を生じさせてしまうのは、やはり「恋」に対する期待値の低さではないか、と思わずにはいられない。
人を好きになる。これは良い。多くの人に生じるであろう感情だ。
しかし、好きになったとして、そのあとはどうなるだろう。
相手にされないかもしれない。振られるかもしれない。そんなリスクがある。
恋人になる。そのあとは?
長く付き合えば喧嘩もするはずだ。相手の嫌なところだって見えてきてしまうだろう。勝手気ままに過ごせる時間も減る。最終的には別れることだってありうるのだ。すべての時間と労力が、たった一言で砂になる。そうなるともはや何も生まない。
仮に夫婦になったとしよう。そのあとは?
どうせ終わる。どうせどちらかが先に死ぬ。どうせ孤独になる。離婚率だって三割ほどある。どちらかの気持ちが変わって、愛なんていうものは雲散霧消するかもしれない。そしたらもう、何も残らない。
すべての人生が直面する、絶対的なニヒリズム。
そういったものに直面するのであれば、最初から本気である必要はない。人を好きになることに期待しすぎないほうがいい。
そんな感性が、この曲の背景にあるのではないだろうか。
だから「かわいい」という繭で自分を包むのだ。ニヒリズムを抱え込みながら。
明るい姿で到来するニヒリズム
いかがだっただろうか。「かわいい」の概念や機能を辿ることで、本曲が宿しているニヒリズムというメッセージを拾い上げることができたと思う。
だが、この解釈を私は「現代社会の云々」というところまで拡張する気はない。人は気分によって聞く曲を変える。本曲も、星の数ほどあるボカロ曲の一曲であり、宿っているメッセージが響く時期もあれば、響かない時期も視聴者各位にはあるだろう。
ただ、この曲が響いた人がいたとして、その理由がうまく言語化できなかったのであれば、本考察が一つの重要な手掛かりになるのではないか。そんなとき、何もかもを手段として見なし、自分でも具体的に何を指すのかわからないような成果に囚われていないか自問してほしい。『チェリーポップ』のようにニヒリズムは案外、明るい姿をして到来するのだから。

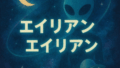
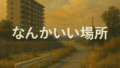
コメント