序章:挫折は身体から始まる
タイトルからして、本曲は「挫折」がモチーフとなっていることがわかる。
Kyikuの『なりきれなかった』という曲がそれだ。
この楽曲を視聴した人の多くは、なるほど、ここに描かれている「挫折」がアイデンティティなどの自己形成に関わるものだと思うのではないだろうか。たしかに「なる」や「なれない」、「できない」という単語は、そんな紐づけを彷彿とさせる。
しかし、本論では、さらに踏み込んだテーマを、本曲の特徴を取り扱いたい。それが「身体」である。改めて歌詞をなぞればわかるが、この曲には「身体」を表象するワードが散見される。「肌の温度」「火傷の跡」や「紐づく身体」など一読すれば、わかってもらえると思う。
したがって本論は、やや抽象的な言い方をするならばなぜ「挫折」と「身体」が、本曲では密接に絡んでいるのか、という点を考察したい。そしてここには現代の私たちが抱えている「身体」に対するイメージが潜んでいる、ということは一旦の結論として先に述べておこう。
一章:喪われた身体とその文脈
少し時間をさかのぼる。ゼロ年代の話をしようと思う。この時代、いや九〇年代から「身体性の喪失」というワードが評論家や社会学者から頻繁に発せられるようになった。理由は明らかである。「生きづらさ」。それに伴う自分を自分で傷つけるという行為が、少年少女の間で流行してしまったこと(南条あや『卒業式まで死にません』など)。そして、ゲームやインターネットのコミュニケーション、例えばmixiなどの仮想生活ゲームによる「身体」の後退が問題視されていたからである。「生きづらさ」を解消するための最後の砦としての「身体」は、仮想現実により、その役目を終えかけているというのがざっくりとした文脈であったように思う。
さて、そこから「身体性」の重要性は復権したのか。少なくとも私にはそう思えない。
このような意思表明に対してすぐに反論があるだろう。確かに最近のフィットネスの隆盛、筋トレブームといっても差し支えないであろう界隈の熱気は、まさしく「身体性」の復権のように思える。
しかし私は、このようなブームは更に、本来あるべき「身体」から遠のいてしまったと感じずにはいられないのだ。改めて見てみてほしい。ブルガリアンスクワットやラットプルダウンなどの身体の加工を。これら実生活から離れたトレーニングや運動は、見せるための、消費財としての身体の研鑽といえるのではないだろうか。失われた「身体」のうえに築き上げられた虚構としての「身体」。換言すれば、「人工物としての「身体」」。これが現在の「身体」に対する通奏低音である。
二章:人工的身体観とその危うさ
さて、そのような観点から『なりきれなかった』という楽曲をみてみよう。例えば「なりきれなかった身体」や「弱くて敏感な肌を襲った不揃い」というワードからは、前述した「人工物としての「身体」」というイメージがある。つまり、身体というのはコントロールすべきもの、デザインできるものであり、すべきものである、という観念だ。
そして本曲で歌われている「挫折」は前述の観念を抱えていたことによるものだといえるだろう。「脆いからもう見ないでよ」や「なりきれなかったここが痛いよ」という痛切な声に耳を傾ければわかると思う。
語り手は、「身体」について、コントロールできるものであるという観念をもっていた。しかし、どうやらそれは挫折に終わった。その理由は明示されていない。ただ、「火傷」や「敏感な肌」などから、個人の努力ではどうにもできない事態があったことは想像できる。だが、ここまで読んでくれた読者諸氏にもわかっているように、身体の完全なコントロール、デザインというのは一つの虚構である。骨格も異なれば、「ブルベ」「イエベ」などの特徴だってある。憧れているところに対してある程度は近似できるであろうが、完璧は無理である。「完璧」こそフィクションである。いうなべれば、『なりきれなかった』の試みは、初めから挫折を運命づけられていたのだ。
結論:「翅」に宿る自然への憧れ
しかし、である。
筆者が思うに『なりきれなかった』の語り部もそのようなことはすでにわかっていたのかもしれない。なぜなら曲中には、自然な「身体」への憧れとも思える箇所があるからだ。例えば「可哀想な翅をただ広げても良い理由」を求めており、そのうえで「自由に飛べるかな」とも語っている。これが「翼」や「羽」ではダメなのだ。「翅」だからこそ意味がある。それは恐らく前者の感じでは「飛行機の」や「プロペラ機の」というように「人工物」のイメージも含有してしまうからである。「翅」は、ただ昆虫のそれしか指さない。そこにあるのは「自然」への憧憬である。
私たち自身も、実は気づいているはずだ。病気をすればどんな頑強な肉体も動かなくなる。歳を重ねれば、いずれ身体は充分な機能を果たさなくなる、と。
そして何より制御可能で綺麗な「身体」というイメージは、「らしさ」によって人々を分断する危険な思想を内包していると勘のいいひとであればお気づきのことだろう。
もちろん、本曲自体には、そこまで踏み込んだ話は出ていないし、想起させるようなフレーズもない。しかし、描かれている「挫折」に共感を覚えるのであれば、それは「完璧」という無謀な虚構の産物だということ、そこからの解放を示してくれているのかもしれない。

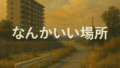
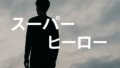
コメント