序論:傑作を再び考える理由あるいは「なんてね」の残響
ボーカロイド曲の傑作といえば多く存在するが、ryoのsupercell『メルト』は、それらの筆頭といえるだろう。すでに十年以上も前の曲になるが「ボカロ曲といえば」という質問には多くの人が本曲を答えるはずだ。
では、この傑作の何を私たちは考察すべきなのだろうか。
いや「あの頃」の名曲だからこそ、私たちは考える必要があるのだろう。
つまり、それは、なぜ私たちは『メルト』という曲に心惹かれたのか。そう。考察の矢印は私たちに向いている。
私たちにとって、この曲に惹かれた「あの頃」とは何だったのか。それを本論では歌詞の特徴から考えていきたい。先んじて予告しておけば、この考察によって私たちは初めて、この曲の唯一にして最大の謎、曲の最後に置かれている「なんてね」の歌詞の意味が明確になるのだ。
一章:ゼロ年代の「純愛」の季節
まず前提を共有しよう。
この曲の発表は二〇〇七年だった。同年は初音ミクが発売された年でもあった。そして特質すべきは、これまではあくまで「初音ミク」というバーチャルなキャラクターという位置づけから歌われる楽曲が多かったなかで、『メルト』は一六歳の女の子が等身大の胸の内を歌い上げるという歌詞内容が他とは一線を画していたことは注目すべきだろう。
では、そのような時代における他のサブカルチャーの分布はどのようになっていただろうか。
特徴を端的にいえば、良くも悪くも「純愛」の季節であり、揺り戻しの時代でもあった。
例えば、ゼロ年代という括りでいえば『世界の中心で愛を叫ぶ』は大ヒットとなったことは多くの人が知るところだろう。しかし、一方で『DeepLove』や『恋空』のようなケータイ小説が、内容の過激さにも関わらず流行した。また少女漫画でいえば『君に届け』が二〇〇六年に連載開催されたが、同ジャンルでいえば、過激な内容である『NANA』もヒットした。さらにいえば『NANA』でいえば、その特徴として家父長的な性別分業的な内容が盛り込まれていることにも注目したい。作中に登場する芸能活動や身近な賃貸契約については、主に男性キャラクターが担っており、一方で女性キャラクター(特にハチと呼ばれる『NANA』の主人公の一人)は、労働についても所謂「腰かけ」程度の熱量しか有していなかった。
「純愛」という装飾のなかに、旧来型の価値規範があったことが当時の景色であり、決して少なくない人が、そんな関係性についてロマンを感じていたのだ。
そして、このスタイルは『メルト』のなかにも潜んでいる。
例えば歌詞には「「どうしたの?」って 聞かれたくて」や「好きだなんて 絶対に言えない…」とあり、先の『メルト』の設定を鑑みれば、語り手である少女は、明確に「選ばれる」準備をしているということになる。あくまで「受動的」なのだ。さて、ここから本曲の最後にある「なんてね」の意味の考察を行うこともできる。しかし、ここでは先の指摘に対してもう少し説得力を持たせてみることを行ってみたい。
二章:『メルト』が描いた時代精神
流行歌というジャンルをみれば、女性の「主体性」もしくは「選ぶ側」であることを明確にしている記念碑的な作品がある。それが一九九五年に発表された広瀬香美『ゲレンデがとけるほど恋したい』だ。「私をネ/失ったらネ/あなたの人生/終わりだよ」という挑発的な歌詞が、そのことを如実に物語っている。
この『ゲレンデがとけるほど恋したい』ほどではないが、二〇一〇年代では、このような積極性が再び歌われる時代となる。その一つの例としてHoneyWorksの『金曜日のおはよう-another story-』を挙げてもいいだろう。
いずれにせよ、九〇年代と一〇年代に見受けられるような「主体性」はゼロ年代は陥没していることは明確にわかったはずだ。これらのことから、私が前節で「純愛」をロマンと言った意味、そして『メルト』の「なんてね」という歌詞の意味がわかると思う。
つまり、『メルト』の「なんてね」は、「ロマン」を「ロマン」として認識しているが故のシニカルなつぶやきなのだ。本曲の語り手である十六歳の少女はわかっていた。私たちもわかっていたはずなのだ。「ピンクのスカート お花の髪飾り」をしても、「「しょうがないから入ってやる」なんて」言われるはずがない。
『メルト』という曲は、たしかにいわゆる「メルトショック」といわれるほどの影響をボーカロイド曲の世界にもたらした。しかし、そんな一つの時代の幕開けは、同曲の最後において、一つの時代の溶解(メルト)をシニカルに直観していた。そのような一つの時代精神を明確に描いたという点で、本曲はやはり傑作なのだろう。
結論:シニカルな呟きの結末は
いかがだっただろうか。
私たちは、このような考察を経て初めて、自身の立ち位置を知ることができた。
しかし、筆者として本論の欠点をいえば、それは現在との比較が出来ていないことが挙げられるだろう。幻影として浮上した十六歳の少女像は、一度主体性を取り戻したあと、二十年代の今、どのようになっているのだろうか。その答えは別の機会に譲ろう。

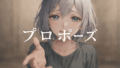
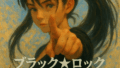
コメント