序章:「書く」の正体をめぐる冒険
『書いて、愛して。』という不思議な曲がある。
この楽曲を考察しようと思ったものの、さてどのような切り口にしようか、と思い悩んでしまった。歌詞を読む限り、仄かにストーリーらしきものはあるようだ。「汚れてしまった君」と「綺麗なままの僕」が書くという行為によって、関係性を紡いでいるらしい。
だが、そこから一つのストーリーをひねり出すには筆者である私の想像力で大部分を補わなくてはならない。これは「考察」というよりも二次創作だろう。そんなわけで却下。
次に思い浮かんだのは、この関係性から現代っぽさを導き出すというものだ。なるほど、これはうまくいきそうだ。誰もが発信者になれる社会的状況と絡めれば、できないことはない。
しかし、である。
作中の登場人物らの関係性と、私たちが想定する社会状況、現代っぽい繋がりには大きな隔たりがある。果たして私たちは、「君」のこと、受け手のことをどの程度想像して、身近ら発信者になっているのだろうか、という隔たりだ。歌詞のなかで「僕」は「君」のことをよく知っているようだ。にもかかわらず、そこに「書く」ないし「発信」という部分だけで現代社会とのつながりをみるのは、かなり強引だろう。うーん、難しい。
こんな問答を繰り返しているうちに、『書いて、愛して。』のなかに描かれている「書く」という行為は何なのか、と思い始めた。本曲で描かれている「書く」というのは隠喩なのではないだろうか、と可能性すら浮かんできた。
そうだ、これでいこう、と思った。本論では、この音楽に描かれている「書く」の正体を紐解いていきたい。
結論を言ってしまえば、本曲で描かれている「書く」は、今の私たちにとって必要なものなのかもしれない。さっそくみていこう。
一章:「まる文字」の話
「書く」という行為、それによって出力される「文字」について、かつて「まる文字」文化というものがあったのをご存じだろうか。それがどのような文字なのかは検索していただくとして、一度でもみたことある人であれば「あー、これね」と思うだろうし、そうでない人は「なんだ、この文字は」と驚くに違いない。
いわゆる「平成レトロ」っぽさを感じる人もいるだろうが、その起源は更に時を遡ることになる。宮台真司『サブカルチャー神話解体』によれば「まる文字」の登場は、七〇年代前半にさかのぼることができる。平成一桁どころではない。昭和二桁である。
さて、学者たちは「なぜこのような文字が多くの女の子に使われ始めたのだろう」と考えはじめ、一つの仮説にたどり着いた。前述の本によれば、この文字は「外向きの奔放な、しかし軽くて傷つけあうことのない対人関係の形成にこそ、その力を発揮する」。
つまり、「まる文字」は、「かわいい」を(意識的にしろ、無意識的に白)対外的にアピールすることによって「お互いに深入りすることは避けよう」という一つの信号なのである。改めて上記の本の中では次のように述べられている。「こうした、対人関係のコードとしてのキュートな「かわいさ」とは、ある意味で、「子ども的」な仲間感覚に近いと言えよう。すなわち、愛らしさ・無邪気さ・明るさ・元気さなどへ誰もが文脈自由に抱く(はずの)共感に依拠して、いつまでも戯れ続けること。各人によっていかにも異なりうる「本当の<私>」を詮索するのをやめにして、「みんな同じ」であることを巧妙に先取りしてしまうコミュニケーション」。この実践が「まる文字」なのだ。
このことを更に俯瞰してみれば、多くの人がそんな「詮索するのをやめにして」という時代の空気を共有していたからこそ、まる文字は受け入れられたともいえる。
読者は、ここまで読んでみて「この話がどうして『書いて、愛して。』の楽曲につながるのだ」とやきもきしているかもしれない。そこで改めて強調しておこう。私がここで言いたいのは、「書く」という行為が、一つの文脈、時代性と結びつき、時代の文脈ともいえるものの共有に役立っていたということである。
二章及び結論:時間・形・震え。あるいは愛
そのように考えれば『書いて、愛して。』という曲に現れる「書く」という行為は、「僕」や「君」にとって自分の主観という文脈を共有するための手段だったのではないか、と私は思ってしまう。文脈を共有すること、換言すれば、主観的な光景を共有できるというのは、孤独を和らげる。
たしかに現代は「文字」や「書く」と言う行為が凶器になる時代でもある。ネット環境をみれば、そんなことは言うまでもないことだろう。しかし一方で、いや、本来的には「書く」というのは、その人の主観を共有するための道具だったはずだ。そう。私たちが「まる文字」の機能で明らかになったことは、伝える内容だけが、伝わる内容ではないということだ。
文字の震え、形、大きさ、消した跡、要した時間。「書く」と言う行為にどうしても付随してしまう、これらの行為が、文字情報よりも多くのことを受け手に伝える。
『書いて、愛して。』のなかに出てくる作品は「詩」のみであるが、「僕」も「君」も、お互いに受け取っているのは、その内容のみではない。描いたもの、裂いたことによって生じた書き直すための時間、そういったもの全てをお互いに伝えあっている。そのことが孤独を抱えた者にとってどれほどのケアになるか。どれほどの安心になるか。きっと力強い「心の拠り所」になるだろう。そういったもので、この二人は結びついている。
だからこそ、と思う。『書いて』のすぐ隣に『愛して』という文字が並んでいる理由。
例え「汚れてしまった君」と「綺麗なままの僕」のように真逆の存在でも、それを結び付けるのが「書く」という行為の奇跡的な力なのではないだろうか。
『書いて、愛して。』という作品からは、そんなことを思わずにはいられないのだ。

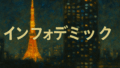
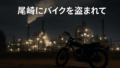
コメント