序章:彗星のように現れた『モニタリング (Best Friend Remix)』
傑作はいつだって彗星のように突如として現れる。
本論で取り上げるDECO*27『モニタリング』はそのように紹介しても決して大げさではないだろう。ここでは『モニタリング (Best Friend Remix)』と『モニタリング』を比較する。これらはそれぞれ「友情」と「推し」あるいは「依存」をテーマとしているが、これらにどのような差異があるのか、歌詞内容から明確にしていきたい。
最初に述べておけば、これらの差異はほんの些細なものだ。どちらも対象に「共感」していることは間違いない。しかし、そこからが違うのだ。
さて、このような作業に、果たしてどのような意味があるのか。この作業は私たちに「友だち」という素朴な概念の在り方を改めて教えてくれる。
かつて「教室はたとえて言えば地雷原」という川柳を中学生が作った。一見すると友人関係のなかにまどろんでいられそうな「教室」という空間でさえ、地雷原なのだ。思い返せば、誰も私たちに「友だち」を教えてくれなかった。スクールカーストの優劣、損得勘定。そういった酷薄な関係性を「友だち」という言葉で装飾しているのではないか。
だからこそ、これからの作業には意味がある。そう。この分析はある意味で私たちへの挑戦状でもあるのだ。
一章:「推し」は背骨、「友情」は介入
まず注目したいのは冒頭部分。
『モニタリング』では「バレてるんだし言っちゃえよ 効いてんの?」となっているところだ。これはBest Friend Remix版において「バレてるんだし言っちゃえば 聞いてんの?」となっている。
前者の「効いてんの」という言葉について、ネットカルチャーに詳しい人であれば説明は不要かもしれない。投げかけられた中傷に対して傷ついていることを「効いている」という。『モニタリング』の「効いてんの」は、要するに、どの程度傷ついているのかを確かめる言葉なのである。
対してBest Friend Remix版は、自身の声が届いているのか、という純粋な疑問の形だ。このような対比を言い換えるならば、前者は、どの程度傷ついているのかを確かめる、心を探る行為なのに対して、後者は「傷ついたこと」は前提としての問い、つまり相手の心を探るようなことは止めているのだ。
いわば、このような「心を暴く」ことは『モニタリング』と同曲のBest Friend Remix版において強烈なコントラストを放つ。
別の例を挙げよう。『モニタリング』では「君の“痛い”感じていたい」となっている部分がある。一方でBest Friend Remix版は「きみのツライ 抱き締めたい」とある。いうなれば、前者は「共感」それ自体が目的であり、後者は、負の感情をどのように処理するか、という具体的行動に重きが置かれている。
ここからは想像になるが、前者は、他者と通じて自身の生を感じるような在り方といえるのではないだろうか。
このように思うのには根拠がある。冒頭でも述べたとおり『モニタリング』は「推し」の歌である。事実「きみを推すことをやめない」という歌詞があるぐらいだ。
このことから想起するのは宇佐美りんの小説『推し、燃ゆ』である。この小説には「推しは私の背骨」と主人公が語る箇所がある。詳細な考察は割愛するが、これだけでも「推し」という行為の重々しさを感じ取れるだろう。「推し」は「生」の屋台骨であり、「推し」の心は自身の心でもあるのだ。『モニタリング』も、「推し」という行為に含有されている「重さ」が現れている。
しかしBest Friend Remix版は異なる。「友情」はやはり「推し」とは違うのだ。
二章:空疎な友情を越えるために
前節のことを引き継げば、Best Friend Remix版において目立つのは、負の感情に対する処理を具体的に述べている点だ。
「きみに重い 暗い思い 除きたい」「分け合って 乗り越えたいんだってば」や更に具体的な行動を表している「心配だから今からそっち行くね」という箇所が挙げられるだろう。特に具体的な行動を示しているのは「友だち」をテーマにした曲にも通じている(Omoi『君が飛び降りるならば』など)。
このような行動偏重な考えが過激に思える読者もいるだろう。
しかし、ここで興味深い指摘を紹介したい。『NewsPicks』における社会学者の宮台真司とメディアアーティストの落合陽一の対談である。
宮台は「友だちの作り方がわからない」という質問に対して「困ってるやつを助ければいいだけ」と回答する。宮台の「友だち」に関する考えは先の対談やコラム『友達って何?』に譲るが、しかし、ここまで読んできた読者であれば、宮台の指摘にはある程度の説得力を感じるのではないだろうか。
想像上の他者の心ではなく、確信。
単なる共感ではなく、他者のために動く勇気。
「友だち」を作るのにも、「友だち」であり続けるためにも、そのようなものが実は必須であり、それを欠いた「友情」などというものは、空疎な戯れに過ぎない。
Best Friend Remix版の『モニタリング』から、そのことは充分にわかるはずだ。「友だちだから面倒だと思われたくない」というのは本質を欠いているというわけだ。
読者諸氏は、このような考えにどのような思いを抱くだろうか。
結論:地雷原を越えて――友情の現在
いかがだっただろうか。
大人となり、すでに働いている筆者にとって「友情」の現在がどのようになっているのか、それを確かめるには難しい年齢になってしまった。しかし『Z世代化する社会』などの本を読む限りでは、たしかにコミュニケーション自体は多様になったように思われるが、やはり「地雷原」の川柳が出来た頃と比べて地殻変動のようなものが起こっているようには思えない。昔、私自身がそうであったように、浅薄で空疎な関係を「友情」と思っている少年少女は、少なからずいると思っている。
しかし、だからこそいえることもある。自分ために怒ったり、泣いたり、傍にいてくれる人を大事にすべきだ。本当に。
恥ずかしながら、これがかつて「地雷原」の教室で、無邪気を装いながら戯れていた先達からの精いっぱいの率直な感想である。

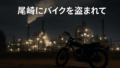
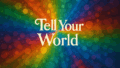
コメント