序論:「ニセモノ」としてのインターネット空間
この曲のテーマについては、多くを語る必要はないだろう。
Ariyou『ニセモノの檻』の主題は明確だ。インターネット空間を「ニセモノ」とする語り手の飢えを描いている。
では、本作を前に我々は何を語るべきなのだろうか。そのための提案として私は次のように問いたいと思う。この歌詞の内容から、我々の本当の欲望、リアルな世界に望むべきものとは何なのかを明らかにしていきたい。
一章:「愛」の偶然性とネット空間の罠
とはいえ、そのような問いに、歌詞は充分に答えていると思う。例えば「愛」。例えば「夢」。そういった単語が歌詞の中にちりばめられている。しかし、この解答の問題は、そのような概念の質が問われていないという点だ。
繰り返しになるが、確かに歌詞には「愛されたい」ということが書かれている。しかしその直後に「一瞬の愛が流れるタイムライン」というふうにネット空間のなかにおける「愛」の質が書かれていることに注目しなければならないだろう。
他にも「夢さえもデータに変わってゆく」とあり、このことは同時に「夢」を渇望しているものの、それは瞬時にデータへ変換されていく性質をもつことがわかる。なるほど、たしかにネット空間における「夢」は、すぐに広告の効率よい配置のためのデータとなり、レコメンド機能によるインスタントな願望充足の呼び水となってしまうだろう。
さて、これらのことを逆照射してみると、歌詞で語られている「愛」は永遠とは言わずとも持続可能性のあるものだし、「夢」は誰にも簒奪されることのないものであることがわかる。
だが、これらのことは現実世界に求めることができないものなのだろうか。まずは「愛」について考えてみよう。これが例えば「恋愛」だと仮定してみれば、確かに現実世界に求めるのは難しいことがわかる。急いで補足するならば、これは「モテ/非モテ」という表層的なことを言っているわけではない。「恋愛」自体の希薄化のことを言っているのである。どういうことか。
このことについて興味深い指摘がある。「恋愛」というものが「偶然」によって生じるという、我々の多くが当たり前と感じていることに対して『サブカルチャー神話解体』という本は次のように述べている。
「一方で、「どんな男の人にも、知らなかった裏の顔がある」という強烈な実感が、「自分は世の中が分かっていない」という「不透明感」を急上昇され、それまでの「自己信頼」を喪失させる。他方で、「一秒遅れれば違う人に繋がったハズ」という、電話コミュニケーションでいきなり直面した過剰な<関係の偶発性>が、人間関係一般に敷衍されて「現実の手触り」が喪失する。(…)「極度に高められた偶発性感覚」が、「関係そのものの基礎のなさ」と読み替えられ、当たり前の[恋愛→結婚]というプロセスが、「きわめてありそうもないこと」として受け止められている」
いささか長い引用になってしまったが、書いていることは分かってくれると思う。それまで地縁・血縁、あるいは地域共同体で基礎づけられたものが喪失した中で生じる「出会い」は、その偶然性ゆえに「ありそうもないこと」として受け止められてしまうということが、ここには書かれている。
これに対して「マッチングアプリなどがある」という反論は的を外していると言わざるを得ない。ここで重要なのは出会いの「偶然性」だからだ。電話やナンパ、あるいはマッチングアプリであろうとそれは変わらない。そして皮肉なことに、ネット空間における「愛」も、この「偶然性(=タイムライン)」が基層となっている限り、状況としては変わらないのである。
二章:「夢の質」への問いを避け続ける社会
次に我々が考えるべきことは、この曲のなかで語られている「夢」についてだろう。ここで描かれている夢は一体、どのような形なのだろうか。データに還元できないとすれば、それはつまり、単位を持たない質、いわば情熱のようなものではないか、と私は思う。ネット空間では夢がデータに変換されるのであれば、現実世界こそ、質量のある夢をはぐくむ場所ではないのではないか。
しかし、どうもそうではないらしい。ネットが今ほど社会のインフラになっていなかった平成という時代について、とある批評家はこのようなことを述べている。
「ぼくは平成の批評家だった。それは、平成の病を体現する批評家であることを意味していた。だからぼくは、自分の欲望に向きあわず、自分にはもっと大きなことができるはずだとばかり考えて、空回りを繰り返して四半世紀を過ごしてしまった」(東浩紀)
本論では仔細に語ることはできないが、「平成」という時代、あるいは社会、もしくは空気は、欲望に向き合うことを許さなかった。
「きみは結局なにがしたいの」という夢の質に対する問いについて「平成」は、あるいはそこで生きていた多くの人は無視を決め込んだのだろう。ネット空間は、「平成」を横滑りさせただけではないだろうか。
少なくとも『ニセモノの檻』で語られている「夢」はそういうものであり、時計の針を巻き戻せないように「きみは結局なにがしたいの」という問いについては、今でも多くの人が苦笑を浮かべながら、肩をすくめるだろう。
結論:抜け出せない檻としてのリアル
このように考えると、歌詞の「抜け出したいけど繋がれたい」「間違えだとしてやめられない」という部分の切実さが、より一層明らかになっていく。
端的に言おう。どうしようもないのだ。
抜け出した先の「現実」、間違えたと思い引き戻した先にある「リアル」は、「満たされない欲望」を満たすことは無い。
このことを直接的ではないにせよ『ニセモノの檻』は暴露したのである。
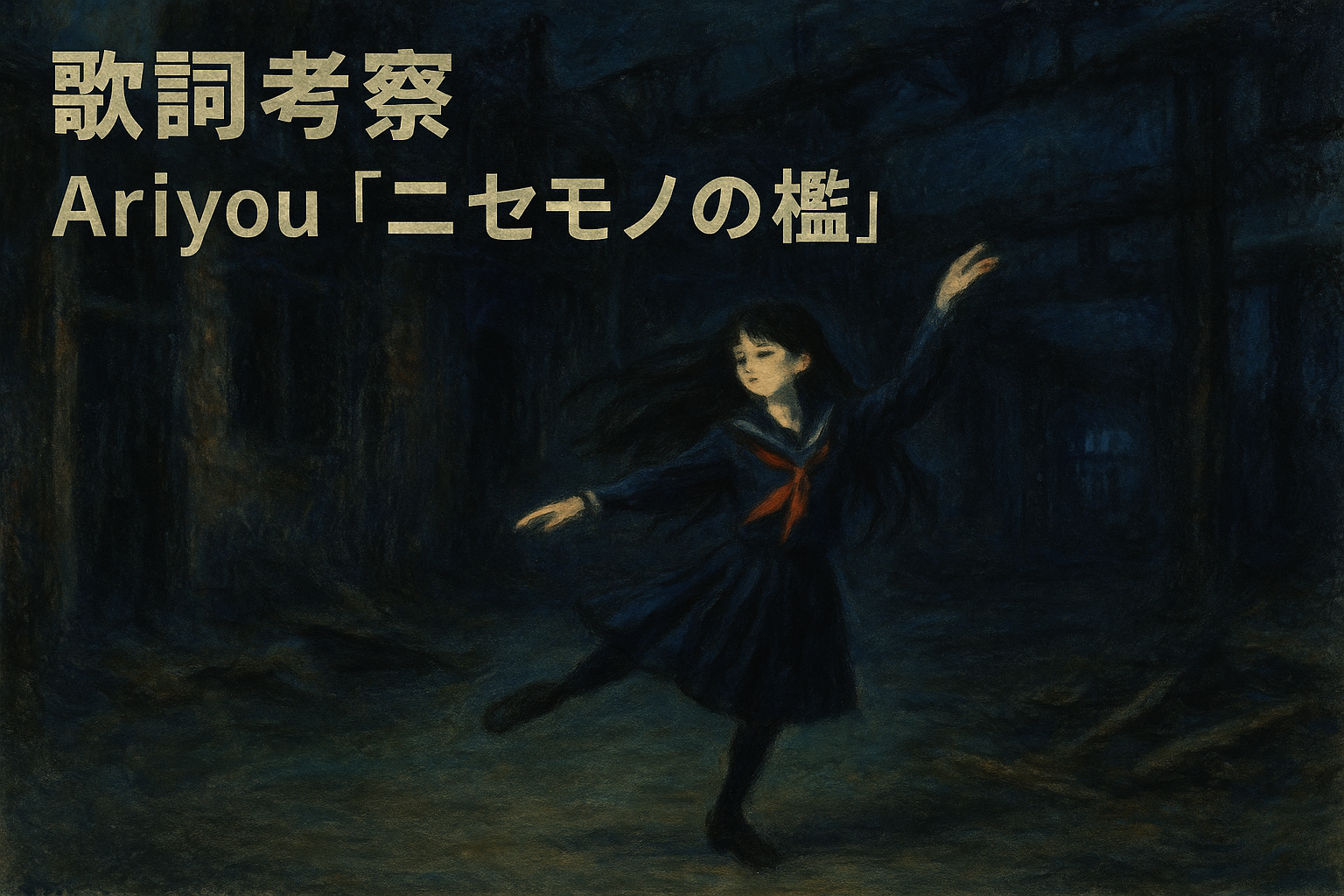
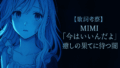
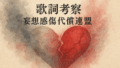
コメント