序章:沈黙していた名前――ハチ=米津玄師
扱うことを避けていたアーティストがいる。
米津玄師である。この人の紹介はもはや不要だろう。そして彼が「ハチ」という名前でボカロPとして活躍していたことは、今や多くの人が知っているのではないだろうか。
本論では「ハチ」こと米津玄師が2017年に発表した曲『砂の惑星』を取り上げる。
さて、そのうえで『砂の惑星』の何を考察すべきか、という問いにすぐさまぶつかるわけだが、ここでは「砂の惑星」とは何処なのか、ということを考えてみたい。
「砂の惑星」とは現実社会の何処かの暗喩なのか。SF的想像力の産物なのか。そして、その舞台に込められたメッセージとは何なのか。これらを考察していきたい。
そのために、2017年という年、ボカロというツール、そして歌詞を結び付けていく。これによって「砂の惑星」の正体は突き止めることができる、というのが本論の立場だ。
では、まず答えだけ言ってしまおう。
「砂の惑星」とは、私たちの心である。
どういうことか。さっそくみていこう。
第一章:メルトショックの記憶――“内面”が生まれた瞬間
この曲がボーカロイドという歴史をなぞっているというのは、実は多くの論者が指摘していることだ。その象徴的な歌詞が「メルトショックにて生まれた生命」である。ボカロ曲になじみのある人であれば「メルト」ないし「メルトショック」という言葉に聞き覚えがあるのではないだろうか。このサイトでも取り上げたことがあるボカロ曲の伝説的名曲『メルト』。そして、その流行の衝撃を「メルトショック」という。
もちろんボカロ自体は『メルト』より前に登場していたが『メルト』がボーカロイドというムーブメントの景色を一変させたことは間違いない。なぜなら、これまで一つのツールであったボカロないし初音ミクはこの曲の登場により、人格を有した”人間”として扱われ、16歳の少女・初音ミクという内面が描かれることになったためだ。「メルトショックにて生まれた生命」というのは内面が「生まれた」ことを示している。
『砂の惑星』の先の歌詞が、ボーカロイドの歴史を意識して作られていることについて、これ以上の証拠はないだろう。
ただ、ここまでの記述は少し調べたことがある人であれば、もはや常識的なことでもある。なにせWikipediaに載っているぐらいなのだ。私たちはそこから一歩先を行かなくてはいけない。
そこで次のように問うてみよう。なぜボカロの歴史を通奏低音としている本曲の舞台が「砂の惑星」などという殺伐としたものとなっているのか。そのために、私たちは次に2017年という年について考えなければならない。
第二章:2010年代の転回――“内面”からの撤退
2017年、いや、2010年代というのはそれ以前のサブカルチャー史において大きな転換点でもあった。その象徴がアニメ監督・新海誠の作品『君の名は』や『天気の子』の登場である。
90年代から00年代までは、『エヴァンゲリオン』が象徴的なように「内面」に重きを置く作品が非常に多く、また多くの視聴者もそのような作品に惹きこまれていた。内面を描いたという点においては先に挙げた『メルト』自体も、そんなサブカルチャーの状況に呼応する作品だったというわけだ。
しかし、『君の名は』や『天気の子』については、「「セカイ」に閉じるのではなく、「この世界」とつながるものになっている」(藤田直哉)、「「セカイ系」的な設定のもと、パーソナルな感情だけにフォーカルを当てていましたが、本作はこのようにして「社会性」を入れることによっても、一気に広がっていくことになります」(土居伸彰)と様々な論者に指摘されている。いわば「内面」からの撤退が始まった時期というのが2010年代だったといえよう。
そして、このような変化は米津自身にも影響を及ぼした。
例えば文芸評論家の藤井義允も次のように指摘する。「米津が自閉空間を志向するのではなく、『YANKEE』(筆者注釈:米津のメジャー1枚目、2014年に発売されたオリジナルアルバム)以降に他者を意識したことはこのような流れに沿うものである」。
ボーカロイドの風景を一変させ、多くの作品が「生まれ」た「内面」は、二〇一〇年代において、そこからの撤退を余儀なくされたのである。
事実、このような「内面」からの撤退を徐々に余儀なくされているという状況は『砂の惑星』においても描かれているのだ。「こんな具合でまだ磨り減る運命」という歌詞、あるいは「メルトショック」という言葉の直後にも「この井戸が枯れる前に早くここを出て行こうぜ」と歌われている。自身の出自である「内面」が描く対象として徐々に先細る感覚と諦念が、これらの言葉ににじみ出ていると感じるのは私だけではないはずだ。
これで改めて、本論の最初の疑問に立ち戻ってみよう。
「砂の惑星」とは何なのか。
それは私たちの「内面」である。ボカロを含むサブカルチャーが「内面」から撤退したが故に「砂の惑星」となってしまった。そんな寂寥感を『砂の惑星』はポップに歌っているのである。
結論:「砂漠」以降の豊潤さに向けて
いかがだっただろうか。もちろん、本曲の切り口は本論で開陳したものだけではない。前節に唐突に登場した「セカイ」という単語から直観的にわかる読者もいただろうが、いわゆる「セカイ系」という文脈や米津玄師という作家にとっての本曲の立ち位置など、その視座の豊潤さは語れど尽きることはないだろう。
そして更にいえば、これまで語った内容はあくまで2010年代のことが中心であり、現代の状況に迫るものではないが『砂の惑星』という一曲から、そこまで導き出すのはあまりにも射程が離れすぎているのでご寛恕いただければ幸いである。
いずれにせよ、「ハチ」が生み出している作品には時代性、批評性、メッセージ性のいずれも優れているものが多いことは間違いない。そんな巨大な作家の作品に対して、本論が読者にとって一定の納得感を与えることができたのなら筆者としては満足である。

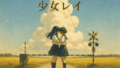
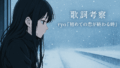
コメント