序論:はじめに――宮沢賢治との邂逅
「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」
これは詩人・宮沢賢治の『春と修羅』にある一文である。
なぜ、このような文章から本論を始めたかといえば、これがハチ(米津玄師)『ドーナツホール』の通奏低音になっているからだ。
急いで補足すれば、ハチ(米津玄師)と宮沢賢治の繋がりについては、決して突飛な話ではない。『カンパネルラ』という歌があるぐらいなのだ。
そのようなわけで、さっそく本論の結論を『ドーナツホール』の歌詞を仔細に分析しながら説明していきたい。
一章:「修羅」と「簡単な感情」――苦悩する語り手
まず触れておかなければならないのは『ドーナツホール』と『春と修羅』の類似点だろう。まず「修羅」のほうだが、宮沢賢治はこの「修羅」という存在に自身を重ね合わせている。事実、彼は「俺はひとりの修羅なのだ」という一文を残しているのだ。ただ、注意しなければならないのは、ここでいう「修羅」は賢治自身の懊悩を象徴する語であるということだ。
詩人・童話作家だった賢治だが、彼が「世直し」を志向していたことはあまり知られなていない。詳細な議論は割愛するが、彼にとって「社会」は強者が弱者を搾取する理不尽なものであった。そして、彼の両親は、そんな二項対立のなかでは「強者」に位置づけられる人間だった。一方で、病弱だった賢治に対して愛情をもって接し、献身的な看病をしてくれたのも「強者」である両親だった。打破する対象でありつつ、自身を救った愛情深い存在。自身の出自に対する愛憎入り混じった感情は、生涯、賢治を苦悩させることになる。
さて『ドーナツホール』の文脈でいえば、この「修羅」と正反対の性質をもつフレーズが「簡単な感情」だが、しかし「語り手」自身も、賢治と同様「修羅」の道を行くことになる。この点は「心がちぎれそうだ」「どうしようもないまんま」というフレーズの繰り返しに象徴されるだろう。
そう。「語り手」は「あなた」の不在に懊悩している。「簡単な感情」に委ねて、「あなた」を忘却する自分。しかし、そのことが許せず、心が引き裂かれそうになっている自分。だが、そんな苦しみも、忘却も「どうしようもない」として、「語り手」はただ佇んでいる。歌詞の中にもあるように「死なない思いがある」という美辞麗句でさえ、「語り手」にとっては「安心なのか」と苦悩しているのだ。そんなことを信じることで「あなた」を忘却することは許されるのだろうか。
『ドーナツホール』の「語り手」に宿る「修羅」は、そんな思いを抱えている。
二章:「有機交流電燈」と「ドーナツホール」――不在を受け入れること
そんな苦悶に対する回答が、実は『ドーナツホール』というタイトルそのものだ。
なぜそのように言えるのか、というのを議論する前に、冒頭で引用した「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」という一文を考えていきたい。繰り返しになるが、これこそが『ドーナツホール』というタイトルの真の意味につながるからだ。
先の「現象」という言葉はシニカルな態度の表明ではない。重要なのは「有機交流電燈」という部分。これ自身は、賢治の造語だが、ここで伝えているのは「私」というものは、「私」自身の内的な確信に依るものではなく、様々な「他者」との交流によって初めて立ち現れる存在である、ということだ。そして、これは、生きている人間という制限を有しない。賢治の著作からもわかるように、彼は自然の擬人化(『風の又三郎』)、幽霊(『銀河鉄道の夜』)、その他生命(『よだかの星』)との交流を描いてきた。そのような世界観から推測すれば、ここの「交流」が、今、目の前にいる他者ではなく、「不在」となってしまった「他者」も含まれることがわかるだろう。それらすべてが「私」という存在を成り立たせているのだ、というのが先の一文の真意である。
同時に、このような世界観を『ドーナツホール』も有している。いや、有するようになったというべきか。
もともと「語り手」は、「ドーナツ」の穴を、「あなた」の不在のことだとしていた。しかし「この胸に空いた穴が今/あなたを確かめるただ一つの証明」という歌詞がそれであるように、「語り手」は、「不在」を追い求めるのではなく、「不在」であるが故に「私」があるという風に転換する。
これは転換はたしかに、苦痛から逃げられるものではない。「語り手」は「それでも僕は虚しくて」と訴え続ける。しかし、そんな「穴」ですら、自身の一部とすることで「不在」も忘却も、忌避すべきものではなくなっていく。
本曲の結末に「目を見開いた」と繰り返され、視覚が強調されるのは、そんな「不在」を認められず、追い求めていた「語り手」が、その「不在」を容認することができたという変化を歌っているのだ。
結論:喪失を生きるということ
いかがだっただろうか。
本曲は、喪失を歌った曲ではない。さらにいえば、様々な出会いや交流に対して、シニカルな視線を奨励するものでもない。むしろ、そういったものは恐れるものではない、ということを歌っているのだ。「どうせ別れる」「この出会いも、交流もつかの間だ」と他者を脅威と感じ、それを一切排除しても、その「不在」によって「私」は形づくられる。
そうであればこそ、私たちは「他者」とどう向き合っていくべきなのか。その答えは聞き手に委ねられている。
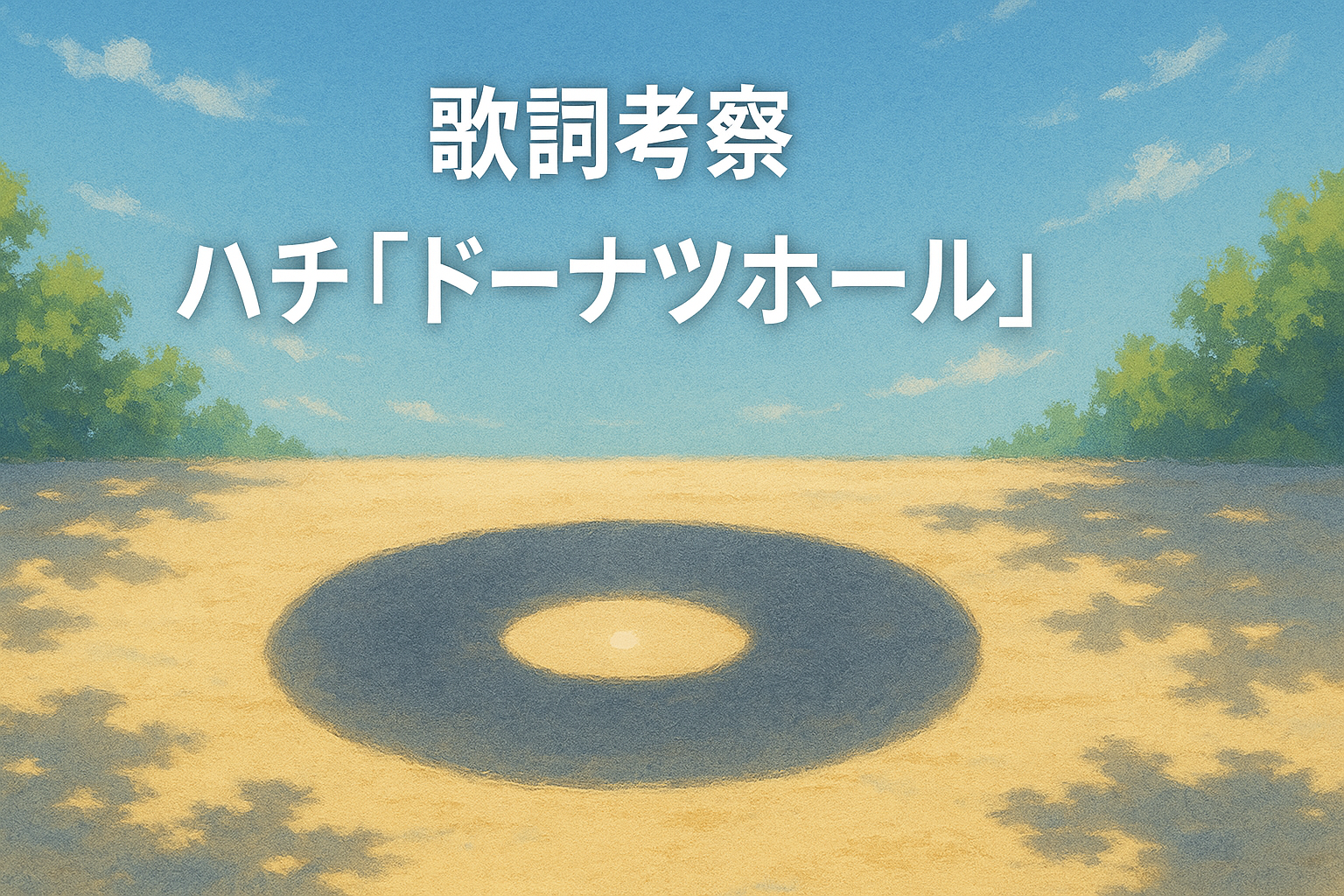

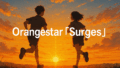
コメント