序論:恋の“可愛らしさ”とその違和感
かわいらしい歌だと思った。
これが、40㍍Pの『恋愛裁判』という曲を聞いたときの率直な感想だ。
それと同時に、思わず苦笑いが漏れてしまう。この曲を漂っている「人を好きになること」に対する浮遊感に。もっとも、このように書いてしまっては読者には何のことだからわからないはずだ。
というわけで本論では、まず『恋愛裁判』の歌詞内容を整理したあと、先の「浮遊感」の正体をクリアにしていきたい。
一章:裁かれる僕、微笑む君──物語の整理
『恋愛裁判』という曲を、やや雑にまとめてしまうならば「痴話げんか」だと思う。一度でも聞いたことがある人であれば、そんな雑感は大過ないと感じるはずだ。
この曲は大きく二つに分かれている。前半は、「僕」と「君」の諍いの様子が描かれており、後半は「僕」の弁明と言ったところだろうか。
急いで補足すれば、本曲は片思いや両片思いの様子を描いた曲ではない。すでに恋仲にある二人の曲である。歌詞の内容から推察すると、「僕」が「浮気」とまではいかないまでも、それに似たようなことをしてしまったのだと思う。「ちょっと魔がさしたんだ」という歌詞からは、そのような背景を読み取ることができる。
そんな「僕」に対して「君」は怒り心頭の様子らしい。「僕」が「そんな眼で見ないで」と弁明する点や「涙の後に」という歌詞から、少なくとも「君」は相当感情的になっていることがわかる。
そして、そんな「僕」に「君」は「有罪」を告げる。これが具体的にどのような行動を指すのか、歌詞の中では明示されていない。しかし、歌詞冒頭の「僕独りじゃ生きていけない」という箇所や、一般的な感覚からしても「君」は「僕」のもとを離れようとしたのだろう。前述した本曲の前半は、こうして終わる。
さて、ここからが可愛らしい。
本曲の後半は「僕」の弁明パートである。例えば「僕は取り繕わないよ」や「ずっと君の監獄に閉じ込めてもいいから」という部分から「僕」の必死さを感じるのは筆者だけではないはずだ。
そうして「僕」は覚悟を決める。「終身刑で償う覚悟/死ぬまで君だけを守るよ」という歌詞は、言葉だけは物騒だけれど、ここまで詳細に説明してきた本曲の文脈を踏まえれば、これの歌詞がプロポーズのパラフレーズだということは一目瞭然だろう。
普通の曲であれば、「僕」と「君」がこのような大団円を迎えたところで終わるのだろう。しかし、そこはテンミリオン達成曲。「僕」と「君」の話には続きがあるのだ。
本曲の最後は「密かに微笑んだ小悪魔/そう、君も有罪」というフレーズで結ばれており、これが示すのは、「僕」が「君」にプロポーズしたのではなく、実は「君」が「僕」にプロポーズさせたのではないか、という疑惑である。
詳細は歌詞の中で明らかにされていない。だが「小悪魔」から洩れる微笑みが、先のような疑惑を読者に植え付ける。
見事な一曲だと思う。
では、次節では冒頭に示した「浮遊感」という謎について述べてみよう。
第二章:恋愛における“操作”の古層
前節では『恋愛裁判』の物語構造を示せたと思う。衝突があり、挽回があり、最後に操られていたかもしれないという疑念が残るといったものだ。この「操り」の感覚というのは、実は非常に古い問題であることは示しておかなければならない。
本曲の特徴である「恋愛」というものにまつわる「操り」の感覚というのは、例えば古くは1973年発表のT.Rex『20th Century boy』にも見出すことができる。
「Well, It’s plain to see you were meant for me」
「Yeah, I’m your toy, your 20th Century boy」
自身を「your toy」としている部分がそうである。
いくぶんか社会学っぽくなってしまうが、この「操り」の感覚が(我々が把握している限りでは)1970年代頃に顕在化したのかについて述べてみたい。端的にいえば、その原因は「消費社会」の到来であると私は思う。奇しくもフランスの思想家・ジャン・ボードリヤールが『消費社会の神話と構造』を出版したのも『20th Century boy』と同じ70年代であった。
「消費社会」とは何か。それは、モノ(商品)を買う行為が欲求充足の他に「自分らしさ」(オリジナリティ)を主張する言語活動の一面となり、他者との差異をつけ、個人のアイデンティティを社会の中に定位させる道具としての側面が一般的になった社会である。
換言すれば「消費社会」は人の印象を「モノ」によって操作することが一般的になった社会だということもできる。この操作の普及が、文化において「操り」の感覚を顕在化させたというのが本論の立場だ。
しかし、これはあくまで、好景気のときの「社会」の在り様。
そこから半世紀程度経過している現代では「消費社会」が変容しており、『恋愛裁判』のものとは質的に異なっているのではないか。そのように考えても不思議ではないが、しかし、アンデシュ・ハンセンが『スマホ脳』などでも書いているよう、現代はSNSを通じた自己演出の時代でもある。
モノを持つ必要はない。
一瞬。
ほんの一瞬だけ、演出ができればいいのだ。
「消費」の内実が多少変化したからといって、モノによる演出によって他者の視線を操作しようとする営み自体は半世紀経過した現在、どこにでも見受けられることだ。
結論:幸福は、理屈の外側にある
「思わず苦笑いが漏れてしまう」
そんな切り出しで本論は始まったと思う。自分なりに、そんな「苦さ」の正体、つまり「変わらなさ」を暴いてきたと思うが読者はどう思うだろうか。
もちろん『恋愛裁判』は素晴らしい作品だと思うし、先に述べた「操り」に対し、その「よし/あし」などというのは正直どうでもいいことである。いや、そのようなことを考えるのはナンセンスだろう。
なぜか。
簡単な問題だ。
『恋愛裁判』に登場する「君」と「僕」の間柄が不幸せそうな色彩を帯びているだろうか。そんなことはないだろう。操られていても幸福である。この逆説こそが、恋愛そのものの本質ではないか。だから、つまり、そういうことなのである。

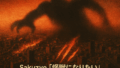
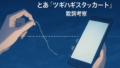
コメント