序論:心がやわらかさを失う前に──二つの言葉の微細な差異
MIMIの『ハナタバ』をはじめて聴いたとき、「愛」や「友情」といったような、どこかの誰かが、どこでも歌っているようなものではなく、「今ここ」に生きている私たちに向けての歌だと直感した。
その直観の契機となったのが歌詞のなかにある二面性だ。
本曲には不思議な箇所がある。それは「空っぽ」と「すっからかん」だ。ほとんど同じような言葉にも関わらず、この作品では前者を「いつしか空っぽな心だけ」とし、後者を「すっからかんに生きたいな」としているのだ。お気づきだろうか。前者がネガティブなニュアンスを含有しているが、後者はポジティブな雰囲気を帯びている。
そう。これが本論の考察の肝要な部分だ。この分離が示すところの意味を明らかにするのが本文のゴールである。
さっそく考察に入るまえに一つの補助線を引いておきたい。その線とは新海誠監督作品『秒速センチメートル』の主人公の台詞だ。社会人の主人公は日々の業務を処理する中で次ようなことを思う。いささか長いが、考察の鍵となる部分でもあるので引用する。
「この数年間、とにかく前に進みたくて、届かないものに手を触れたくて、それが具体的に何を指すのかも、ほとんど脅迫的とも言えるようなその想いがどこから湧いてくるのかも分からずに、僕はただ働き続け、気づけば日々弾力を失っていく心がひたすらつらかった。そしてある朝、かつてあれほどまでに真剣で切実だった想いがきれいに失われていることに僕は気づき、もう限界だと知った時、会社を辞めた」
さて、この「弾力を失っていく心」をヒントに、私たちは『ハナタバ』の考察に進もう。
第一章: 後ろ向きの「空っぽ」──弾力を失う心について
本作における「空っぽ」という語は、一般的に想起されがちな透明で中性的な空虚ではなく、むしろ負の重みをもった状態として提示されている。歌詞冒頭の「止まることもただ怖くて」という一節には、走り続けることを前提とした焦燥が染み付いている。主体は、前へ進むことをやめると自分が崩れてしまうのではないかという脅迫観念のもとで、絶え間なく自己を駆動させてきた。しかし、その加速は心の柔らかさを消費し続ける運動でもあった。ここで参照点として浮かび上がるのが、『秒速5センチメートル』の主人公が語った「弾力を失った心」である。かつて切実であった願いがその輪郭ごと失われ、気づけば世界が色を失っているという体験は、まさに本曲で記述される「いつしか空っぽな心だけが」という感覚と深く共鳴する。
この「空っぽさ」は、俗に言う“虚無”とは異なる。そこには喪失の過程があり、摩耗の痕跡がある。主体は何かを捨てたのではなく、走り続ける過程で「こぼれ落ちてしまった」のである。だからこそ、この空白には痛みが伴う。それは自己の停止や破綻を恐れ、無理に前進し続けた末に訪れる種類の空虚であり、主体の意志ではなく、疲弊した心の側が「もう持たない」と告げるような状態である。言い換えれば、この空虚とは「自分の形を保つための柔らかさ」を失い、外界との接触にもはや耐えられなくなってしまった心の姿である。
さらに重要なのは、この後ろ向きの空っぽさが世界の知覚そのものを変質させる点だ。色彩を失った世界は、本来の豊かさを示すのではなく、主体の心の弾力を失った鏡像として立ち現れる。世界が“空っぽ”なのではない。心の側が空白化した結果、世界がそのように見えてしまうのである。したがって、この「空っぽさ」は単なる比喩表現に留まらず、主体と世界の関係性の転倒を示す構造的な問題として理解されるべきだ。
以上のように、一つ目のポイントとして提示される「後ろ向きの空っぽ」とは、失われた熱情、摩耗した心、そして色を失った世界という三層構造が重なり合った状態である。それは避けたいものであり、また主体が望んだものでは決してない。しかし、その否定的な空白こそが、後に登場する「すっからかんで生きたい」という肯定的な空白と対照をなす基盤となる。
第二章: すっからかんで生きたい──空虚への欲望の正体
『ハナタバ』における二つ目の核心は、「すっからかんで生きたい」という欲望が、先ほど論じた後ろ向きの空虚とはまったく異なる質を持っているという点である。このフレーズは一見すると、先に描かれた空虚への恐怖や心の摩耗と連続しているようにも見える。しかし、歌詞が表現しているのは“空っぽになること”そのものへの賛美ではない。むしろ、あの疲弊した空虚から距離を置き、心を縛る強迫観念の外側へと出ていきたいという主体的な希求である。
焦燥に追い立てられる生の形式は、常に「まだ足りない」「もっと進まなければ」という内的音声とともにある。その音声は主体の歩みを加速させるが、同時に弾力性を奪い、世界の色を奪う。だからこそ、「すっからかんに生きたい」という語は、消耗の果てに到達する虚しさではなく、その強迫的な駆動から自らを解き放つ解放運動として読まれるべきだ。主体は空虚を求めているのではなく、“空虚ではないものに囚われすぎた心”から自由になろうとしている。
この欲望の本質は「軽さ」にある。重荷のように背負い込んできた期待、義務、焦燥、足りなさの感覚──そうした諸々をいったん棚に上げ、身ひとつで風に当たりたいという願い。「すっからかん」という語の響きに漂う軽快さは、本曲における後ろ向きの空白とは明確に異なる態度を表している。それは空虚の“結果”ではなく、軽やかな“選択”である。
さらに重要なのは、この軽やかさが主体の能動的な選択として提示されている点だ。弾力を失った心から世界が“空っぽ”に見えるとき、主体は受動的に虚無へと追いやられる。しかし、「すっからかんに生きたい」と願う主体は、その虚無に呑まれた自分をただ観察するだけでなく、そこから逸脱しようとする意志を持っている。この対照は、曲全体の構造を貫く重要な軸となっている。
また、この欲望は自己の“再編成”とも結びついている。いったんすべてを置き去りにすることで、心は再び柔軟さを取り戻す可能性を持つ。極限まで張り詰めたゴムが切れる前に、もう一度たわみを取り戻そうとするように。ここでの「すっからかん」は、破綻の予兆ではなく、再生のための余白である。人が何かを取り戻すためには、一度手放すことが必要だという逆説が、このフレーズの内側には潜んでいる。
結局のところ、「すっからかんに生きたい」という欲望は、後ろ向きの空虚とは異なる“前向きの空白”として機能している。主体にとって必要なのは、空虚そのものではなく、追い立てられるような生き方からの離脱であり、心が再び世界の色を受け取れるだけの軽さを取り戻すことだ。ここに第二のポイントの核心がある。
結論: 君という存在と〈花束〉──根のなさが示す関係のかたち
本作において最も繊細な意味を担っているのが、「君」という存在の位置づけと、その君に「花束」を並置している箇所である。歌詞の中で「どうしたの?って問いかける無邪気な声」や「君と踊る時間」といったフレーズは、主体の心に色彩を取り戻す契機として作用している。それまで世界は空虚として知覚され、主体の心は弾力を失っていた。だが君という存在を経由して初めて、主体は再び世界に意味や温度を見出し始める。つまり、君は主体を救済する“根源的な他者”としての機能を果たしていると言える。
しかし、本作における花束には決定的な特徴がある。それは “根がない” ということである。花束とは、切り離された花々が束ねられたものであり、大地や根源から永続的な栄養を得ることはない。それは一時性、軽やかさ、そしてどこへでも飛んでいってしまう可能性を孕んでいる象徴だ。
この「根のなさ」は、主体が君に“定住”を求めていないことを示唆している。君がいれば世界が救われるのは確かだが、主体はそこで完全に安住しようとはしない。むしろ、君という存在を通じて世界に色が戻ったことを喜びつつも、自分自身が依存によって再び停滞することを避けたいという慎みが表れている。言い換えれば、この関係は「結びつくが絡みつかない」関係であり、現代的な“軽やかな親密さ”の象徴と言える。
ここでの花束は、重くない献げ物であり、住処ではなく、一瞬の祝福である。君は主体を立ち直らせるきっかけであっても、主体が全存在を預ける場所ではない。根のない花束を差し出すという行為には、関係性に過剰な重みを乗せないという主体の選択が静かに刻まれている。これは、現代的な人間関係の特徴──相手を必要としながらも、過剰な密着を避ける態度──とも巧みに共鳴する。
また、この花束の「根のなさ」をどう理解するかは、聴き手に委ねられている。軽さを求める自由の象徴と捉えることもできれば、現代社会で「根を張る場所が見つけにくい」という諦念の象徴とも読める。歌詞はその両義性を保持しており、そこにこそこの曲の開かれた魅力がある。根がないからこそ、花束は誰にでも手渡され得るし、どこへでも行ける。主体と君の関係性もまた、固定よりも流動を基調としているのだ。
結果として、「君」と「花束」というモチーフは、主体が再生への手がかりを得ると同時に、依存しすぎず、軽やかな距離感を保とうとする複雑な心の動きを象徴している。それは救済と自立、親密さと自由のあいだに揺らぐ現代的な心性を見事に表現していると言えるだろう。

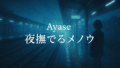

コメント