こんな人におすすめの曲!
- 「感情があるのに、言葉にできない」と感じたことがある人
- 「普通になれない自分」を責めてしまう人
- 「誰にも言えない痛み」を抱えて生きている人
導入――『命ばっかり』は、心が壊れたあとの言葉でできている
ぬゆりの楽曲『命ばっかり』には、何かが終わったあとの風景が広がっている。恋でも人生でもない。
終わったのは、「感情をまっすぐ信じられる自分」そのものだ。
そのようななかで語り手は不格好な言葉をひとつずつ口にしていく。だが、そのどれもが断片的で、輪郭を持たない。まるで、感情の形を取り損ねたまま積み重ねられていくようだ。
誰かと分かち合うことも、自分のことを好きになることも、「普通」でいることさえもうまくいかない。「正しいこと」を目指した結果、置いていかれてしまった。存在するのは、問いかけに対して意思が示されない応答だけだ。ここには、誰かに何かを伝えたくても、それがもう言葉にならないという、深い諦めと、なお残ってしまう願いがある。
『命ばっかり』に描かれているのは、悲しみでも絶望でもない。もっと静かで、鈍くて、そして長く続く“感情の行き場のなさ”だ。
誰かと近づきたい。わかり合いたい。けれど、言葉がうまくつながらない。伝えようとするたび、言葉がこぼれ落ちていく。
それでも語り手は歌う。「遠くへ」と何度も繰り返しながら。どこかへ行きたいわけじゃない。忘れられたいわけでもない。
たぶん、それはただ、このまま何も伝えられずに終わってしまうことが、どうしようもなく怖いからだ。
『命ばっかり』は、そうした壊れかけた心が、最後に絞り出すような言葉でできている。だからこそ、私たちはその不器用な声に、強く惹かれてしまうのかもしれない。
本論――言葉がすり減ったあとで、なお語りつづけること
A. 構造分析──遠くへ行けない感情の反復
ぬゆりの『命ばっかり』の歌詞は、時間的な物語ではなく、行き場のない感情が静かに滞留し続ける構造を持っている。冒頭「日々を磨り潰していく 貴方との時間は」という一節からもわかるように、語り手は変化や進展ではなく、“すり減り”によって時間の感覚をつかんでいる。そして、その関係性は「おかしくなってしまった」ものとして語られるが、それは相手との関係が破綻したというより、自分の感情そのものが歪んでしまったことの告白に近い。
さらに、歌詞の構造には「問いかけ」と「すれ違った応答」が何度も現れる。たとえば「どうしたいの」に対して「どうもしない」と返される場面は、実質的なやりとりが成立していない象徴的な瞬間である。しかもその後に〈貴方はもう何も教えてくれないの〉と続くことで、語り手が本当に欲していた言葉が得られなかったことが示されている。これは会話というより、独り言に近い感情の往復であり、語られるより先に沈黙が場を支配しているのだ。
B. フレーズ精読――語られなかった感情に触れるために
ここにきて『命ばっかり』のなかで最も反復される印象的な言葉の意味が変わる。それが「遠くへ」というフレーズである。この繰り返しは、決して積極的な意志や希望を指し示すものではない。むしろ語り手が〈動けない〉とすでに語っているように、これは「行きたい」という能動的な選択ではなく、「ここにはいられない」という否定の感情からくる消極的な願望である。そしてそれに続く〈動けない僕のことを忘れて〉という一文が、その意味を裏打ちする。ここには、忘れてほしいという意志以上に、「きっと忘れられてしまうだろう」と語り手が予感し、その結末を先回りして口にしてしまうような防衛的な態度が表れている。
このように、『命ばっかり』には語られていないことをめぐる想像が何度も浮上する。
たとえば「知らないを知りたかった」という一節は、何かを理解したいという願望と、それに到達できなかった事実との落差をはっきりと示している。この「知りたかった」の主語が「相手」なのか「自分」なのかは曖昧だが、だからこそ、語り手は相手との距離だけでなく、自分自身の内側とも接続不全に陥っているのだとわかる。
語り手の感情表現には、一貫して曖昧さと控えめさが漂っている。感情を断定せず、未然のまま語るこの言い回しは、自分の気持ちを最後まで信じきれなかった人物像を浮かび上がらせる。
そしてその不確かさは、語りの調子だけでなく、言葉の選び方にも現れている。
曲中にちりばめられている、救いを求めつつも役に立たない存在を匂わせるフレーズは、自嘲と願望がねじれながら同居する瞬間だ。「救われたい」という欲望は明確に示されているのに、それを自嘲的に言い換えることによって、その欲望はどこかで軽んじられ、他者にとって煩わしいものだという自己否定的な評価が同時に入り込む。
さらに重要なのは後半に登場する
「普通に固執することが/怖くてもう泣きそうだ」
という一節だ。この「普通」という言葉が意味するのは、たとえば恋愛、進学、就職といった“誰かの人生”に準じた生き方かもしれない。語り手はその「普通」にどうしても乗り切れず、それに執着しようとする自分自身をどこかで信用できていない。
だから「泣きそうだ」と語る。涙は強い感情の表出ではなく、「泣きそう」という曖昧な予兆として語られることで、語り手の感情が一度も全開にならないまま濁流のように流れていくさまが印象づけられる。
そして、歌詞の終盤に繰り返される「薄っぺら」という言葉。これは三度重ねられた後、最後には自分しか残っていなかったと語る。
このくだりは自己否定のピークというより、否定された自己をようやく“名指す”ことができた瞬間として読むべきだ。
語り手は、語彙を失いながらも、それでも自分の形をつかもうとする。その過程で「薄っぺらだ」と繰り返すことは、自分を傷つけるためではなく、自分という存在の“厚み”を測るための仮の言葉なのかもしれない。
『命ばっかり』において、語り手は感情を確かめるたびに、その輪郭がぼやけていくような体験をしている。
だからこの歌は、愛の歌でも別れの歌でもなく、「感情が確信に至らなかった人の歌」だ。
それでも語り続ける。そのこと自体が、語り手にとっての“命ばっかり”なのだろう。
C. 社会状況との照合――願いが言えなくなった時代の声
『命ばっかり』の語り手は、感情を持っているが、それをうまく言葉にできない。質問しても、応答のないまま会話が終わってしまう。けれど、それに対して怒ったり、責めたりすることはない。ただ、「救われたいと喚くだけ」と語る。
ここには、言葉が通じ合うことをどこかで諦めている人格のかたちがある。
このような語りが生まれてくる背景には、現代のコミュニケーションの特徴がある。
SNSのような常時接続型の環境では、過度に重たい言葉や感情の表明は「うざい」「重い」と敬遠されがちだ。だからこそ、はっきり言わないこと、明確な意思を持たないことが、“気を遣える人”として受け入れられやすい。
『命ばっかり』の語り手もまた、まさにそのような「思っていることを直接は言わない」語り方に身を委ねている。
このように、何かを求めること自体が「面倒」や「迷惑」として拒まれる社会の中で、語り手ははっきりとした願いや怒りを口にすることができない。だが、そのかわりに、言葉にできなかった感情の名残をひとつずつ拾い集めていく。
だから『命ばっかり』は、自己主張ではなく、感情の余韻だけで編まれた歌なのだ。
このような語り方が、多くの人の心にしみ込むのは、私たちがすでに「感情を叫ぶことに慎重にならざるを得ない時代」に生きているからである。何も言えなくなったあとで、それでも言葉を手放さずにいる――その姿が、この歌に深い共感を呼ぶ理由なのだ。
結論――語り続けることでしか、生きていけなかった
『命ばっかり』というタイトルが示すのは、感情をうまく言えず、思いも伝わらず、それでも命だけが残ってしまった人の姿である。
それは、誰かに選ばれることも、深くつながることもできなかったけれど、ただ生きて、日々の中で静かに痛みを抱えている人のかたちだ。
この歌の語り手は、明確な感情を持てないまま、「好きになりたかった」「救われたかった」と言い残す。
そのどれもが、断定ではなく未然のまま語られていて、私たちはそこに、確信ではなく予感のような感情の震えを見る。
けれど、その不確かな言葉こそが、現代を生きる多くの人の感情のリアルに重なるのではないだろうか。
語ることは、もはや誰かに伝えるための行為ではない。
言葉が届かなくても、感情をうまく名指せなくても、語り続けることには意味がある。
それは、「まだ終わっていない」「まだ壊れていない」という、かすかな祈りと抵抗のかたちでもある。
たとえ何も伝わらなかったとしても、語りつづける。
『命ばっかり』は、その姿勢そのものを、たしかなかたちで私たちに見せている。
※本記事は、楽曲の評論・批評を目的として歌詞を一部引用・参照しています。著作権はすべて権利者に帰属します。

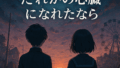
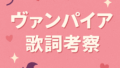
コメント