こんな人におすすめの曲!
- 「本当の自分」がわからなくなっている人
- SNS や Vtuber文化に親しみつつも、どこか虚しさを感じている人
- 他者とつながれないまま、傷ついてしまった人
Ⅰ. 導入・問題提起|「偽り」が日常になった世界で
ツミキのボーカロイド楽曲『フォニイ』(2021)は公開直後から再生数を急伸させ、「現代的虚構の象徴」とまで称されるようになった。歌唱を務める歌愛ユキの無機質な幼い声が「――あたしって何だっけ」(ツミキ「フォニイ」2021)と繰り返すたび、聴き手の内側で現実と虚構の境界が揺らぐ。本作は、単なる “嘘をつく少女” の物語ではなく、自己と他者の関係が希薄化し、世界全体がフェイクで覆われつつある――そんな現代的不安を映す歌だ。
本稿では『フォニイ』を読み解く鍵として、筆者独自の二つの概念〈自己の希薄化〉と〈代理技術〉を導入する。〈自己の希薄化〉は1990年代以降、人間関係を「キャラ」や「役割」でしか築けなくなった社会的傾向を指し、〈代理技術〉はVtuberやSNSのように身体を介さず自我を表象する技術を総称する。
語り手 “あたし” は、まさにその接点に立つ存在だ。歌愛ユキという「声」自体が自己ではなく、イメージを拡張するインターフェースとして機能している。まず両概念の定義と背景を整理し、次に楽曲に顕れる〈声と身体の分離〉と〈他者との接触不全〉を検討しながら、この歌が私たちに突きつける「存在することの困難さ」を浮き彫りにしていきたい。
Ⅱ. 本論|「声」という代理に託された、自我の亡霊
〈自己の希薄化〉をまず定義しておく。この概念は、ポスト・バブル期以降――とりわけ「キャラ消費」が加速した1990年代半ばから顕著になった傾向である。かつて“私”は内面の統一性によって成立していたが、SNSやメディア空間が拡張した現代では、個人は複数の自己=キャラを場面ごとに使い分ける。結果として主体は一貫性を失い、外面的な表層へと希薄化していく。
『フォニイ』冒頭の「この世で造花より綺麗な花は無いわ」(ツミキ「フォニイ」2021)は、〈本当の自分〉を保証する基盤が失われた時代の自己告白だ。世界がフェイクで満ちている以上、主体も“フォニイ=偽物”へと転化せざるを得ないという構図を端的に示している。
ここで接続するのが〈代理技術〉である。これは自己が他者と直接絡むのを回避し、Vtuber・SNS・音声合成ソフトなど代理的媒体を介して関係を築く傾向を指す。『フォニイ』では歌愛ユキ(ボーカロイド)そのものが代理であり、彼女の声は身体性から解放された匿名的データとして響く。〈自己の希薄化〉と〈代理技術〉は相互増幅的だ――“本当の私”を差し出さずとも社会に参与できるからである。
サビの「簡単なこともわからないわ/あたしって何だっけ」は、アイデンティティの揺らぎではなく、“あたし”が空洞化した主体であるという直視にほかならない。さらに「鏡に映り嘘を描いて自らを見失った」という一節は、セルフプロデュースの苦痛を象徴し、代理的な自己演出が自己欺瞞へ雪崩れ込む過程を示す。
興味深いのは、楽曲が“声”を前面に出しながら“身体”を描かない点だ。〈湿った前髪〉や〈鏡に映る顔〉といったディテールも、身体の実感というより映像的な記号として提示される。同系統の恋愛曲が現実の相手を想定するのに対し、『フォニイ』では他者との接触手段そのものが曖昧である。だからこそ「なぜここが痛むのでしょう」という問いは他者との摩擦ではなく、自壊による痛みとして響く。
こうした表現が2021年に強く受容された背景には、パンデミック下の孤立感、SNS依存、そして形のない承認欲求の膨張がある。言い換えれば、『フォニイ』は「他者と接続しないまま孤独を歌う」楽曲であり、その孤独に共振する若者の“いま”を射抜いたのだ。
Ⅲ. 結論・余白の提示|「フォニイ」が残した“声”のかけら
『フォニイ』は〈嘘に絡まっているあたしはフォニイ〉というリフレインを重ねつつ、決して“本当の私”に到達しようとしない。むしろ到達を放棄することによってのみ生き延びる主体の歌である。ここで嘘はただの欺瞞ではなく、生存戦略としての仮面となり、ボーカロイドという技術自体がその「仮面としての声」を体現する。まさにこの構造こそが〈自己の希薄化〉と〈代理技術〉の交差点にほかならない。
ラストの〈造花だけが知っている秘密のフォニイ〉という一節は、本物の花ではなく偽りの中にこそ微かな真実が宿るという逆説を提示する。答えの見えない時代であっても、私たちがなお声を発することに意義が残る――たとえそれが“誰かの代理の声”であっても。
「私は偽物だ」と名乗り出る声こそ最も真実に近い。矛盾を抱きしめながら歌う『フォニイ』は、この不確かな時代にあって誰よりも「本物」の歌である。
※本記事は、楽曲に対する批評的・文化的な考察を目的として、歌詞の一部を最小限に引用しています。著作権はすべて原作者・著作権者に帰属します。

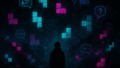
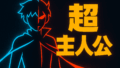
コメント