こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 本曲にどこか哀しさを覚え、その正体を知りたい人
- なぜMVがネットミームだらけか知りたい人
I. 導入――恋はもう安全圏にはないけれど
耳に残る「:-b ;-b boy」という絵文字のリフレイン、そして胸の奥をくすぐるようなシャウト。『テレパシ』は、軽快なビートに乗せてリスナーをいたずらっぽく手招きしつつ、“伝わらなさ”という静かな切なさをそっと差し出してくる。
「あいうぉんちゅーコールが聞こえなーい」
この短い叫びには、せっかく伸ばした指先が空を掴むようなもどかしさが詰まっている。ここで可視化されるのは「好き」という磁力よりも、つながろうとする行為そのものがはらむ微量の危うさ――〈他者のリスク化〉だ。そして歌詞のあちこちに散りばめられた “エンド” を示唆する言葉たちが、私たちをそっと後ろ向きの時間へ連れてゆく。
「勝ちに行って負けるの何回目」
語り手は、終わってしまった舞台装置の隙間からもう一度スポットライトを探し当てようとしている。それが筆者の独自概念である〈アフター系〉――“すべて片付いた後、ほこりの立つ床で再び物語を始める態度”と重なる。本稿では、〈他者のリスク化〉と〈アフター系〉という二つのレンズを中心に、さらに橋渡し役として〈代理技術〉を挟み、『テレパシ』が鳴らす“壊れかけの電波”**を読み解いていく。
II. 本論――リスクと残骸を踊るテレパシー
『テレパシ』を貫く電流は、三つの概念――〈他者のリスク化〉、〈代理技術〉、そして〈アフター系〉――が絡まり合いながら脈打つリズムだ。まず、炎上が日常化した2010年代後半以降、他者は「甘い癒し」ではなく「簡単に牙をむく不確定要素」として立ち現れた。やや大げさな表現のように思われるかもしれないが、この「他者のリスク化」は大なり小なり私たちの身近にある。ここで本曲が、いわゆる「ネットミーム」だらけなPVであることを思い出してみよう。「ネットミーム」は、確かに同系の仲間については連帯の呼び水になるが、そうではない人たちには、いわば「寒いギャグ」「ひどい身内ノリ」のように映るだろう。まだ、マスメディアが今より力を持っていた頃は、このようなことは無かったはずだ。流行は誰にとっても流行であったからだ。しかし「ネットミーム」という細分化は、そのような見知らぬ他者と分かり合える可能性を提示すると同時に、不信の種にもなる。
そこで差し出されるのが〈代理技術〉だ。絵文字「:-b ;-b boy」の軽やかさは真正面の告白を緩衝し、SNS というバッファを経由することでダメージを和らげる。ネットミームを使い分け、言葉も使い分け、自分というキャラはSNSのアカウントのように細分化する。だが同時に、回線上の感情はホワイトノイズを巻き込みながら拡散し、本来の輪郭を失っていく。すべてが「冗談のような本当」であり「本当のような冗談」に霧散していく。「あいうぉんちゅーコールが聞こえなーい」という嘆きは、そんな増幅し過ぎた電波が自らをかき消してしまう逆説を示している。
そして舞台は“終わりのあと”へと滑り込む。「アンハッピーエンドじゃつまんない」と結末を茶化し、「大好きの壁打ちやっています」と相手不在の独唱を続ける語り手は、まさに〈アフター系〉的地平――物語の瓦礫の上でなお小さく灯をともし続ける態度――に立っている。希薄化した自己は代理技術を抱え、リスク化された他者へ向けて送信を繰り返す。そのループがビートとなり、飽和したテレパシーは〈ザッピング〉へ変質しながらも、最後には叫び声の純度へ磨き上げられる。
こうして『テレパシ』は、傷つく危険を孕んだまま、ネットミームというリスクを承知しても、それでも「もう一度」を欲しがる心の動きを、軽やかな絵文字と冗談っぽい歌詞の間に挟み込む。三つの概念は、好きとリスク、緩衝とノイズ、終わりと再演という三層の往復運動を生み出し、楽曲全体を“壊れかけの電波”に変える。届かないコールの残響こそ、この時代を生き延びるための静かな呼吸音なのかもしれない。
III. 結語――届かなくても、声は発される. 結語――届かなくても、声は発される
他者はリスクであり、通信は飽和し、物語はすでに一度幕を閉じた。それでも語り手は声を上げる。絵文字もスラングも剥がれ落ちた先に残るのは、届かないことを知りながら、それでも手紙を投函するような静かな勇気だ。
『テレパシ』が差し出す問いはシンプルで優しい――「それでも、あなたは呼びかけることをやめますか?」 ノイズだらけの時代に、私たちは「伝わる」ことだけをゴールに据えるのではなく、“伝えようとする行為”そのものを抱きしめる道を選べるかもしれない。
〈“feat. きみ”を ねえもっとちょうだい?〉
このフレーズは「成功したい」わけでも「報われたい」わけでもない。ただ、終わった後にも伸びていく夜の蔓のように、断絶を抱えたまま関係を続ける体温を欲しがる声だ。もしあなたの耳が少しでも開いているなら、遠くで微かに重なる誰かのテレパシーに気づくかもしれない。その瞬間、リスクだらけの世界の片隅で、小さな共鳴が息を吹き返すのかもしれない。
※本記事は、DECO*27『テレパシ』の歌詞を批評・研究目的により最小限引用しております。著作権はすべて原権利者に帰属します。

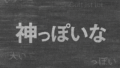
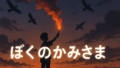
コメント