こんな人におすすめの曲!
- 失ったものを祈りながら、次に進もうとしている人
- 明確な答えよりも、“わからなさ”を抱え続けている人
- 誰かとのつながりを諦めたくないけど、踏み込むのが怖い人
導入――壊れた神話の残骸で、少年はなぜ立ち止まらないのか
夕立に溶けるカラスの羽ばたき、地面にのしかかる影の群れ。羽生まゐごの楽曲『ぼくのかみさま』(2024)は、開幕一行目から“世界の終わり”ではなく「世界がぽっかり歯抜けになった後」の静寂へと私たちを投げ込む。宗教的全能者を思わせる〈かみさま〉はすでに応答を失い、少年の呼び掛けはただ反響のない空に擦過音を残すのみだ。それでも彼は二度三度「行かなくちゃ」と呟き、見えない誰かに向けて狼煙を掲げる――消えかけた物語を延命させる最後の儀式のように。
本稿は、この歌に潜む運動を筆者独自の批評概念〈アフター系〉を中核として読み解く。併せて、1990年代以降の系譜を刻む〈自己の希薄化〉、2010年代の〈代理技術〉、2010年代後半以降に顕在化した〈他者のリスク化〉、そして2020年代特有の〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉を連鎖させ、少年の狼煙が現在の我々にどのような感情の火種を残しているのかを探りたい。
本論――灰を踏みしめ、煙で距離を測りながら歩く一つながりの思考
1990年代、バブル崩壊が露呈させたのは、急速に〈自己の希薄化〉が進行する社会であった。欲望もアイデンティティも輪郭を失い、人々は自傷や他者依存へと震える針を倒した。『ぼくのかみさま』の主人公も「大人にはなれないぼく」と自認し、自らを固着させる確かな言語を持たない。その空洞を埋めるべく見上げた先にいた存在が“かみさま”である。しかし二十一世紀に入り、SNSやアバター、生成AIが浸透すると、人と人との接触はスクリーン越しの安全圏へ退避し始めた。これが〈代理技術〉**である。直接触れれば傷つく危険を、透明なインターフェースが中継してくれる——はずだった。
けれど2010年代後半、タイムラインを覆ったのは炎上と誤爆の恐怖だ。他者はもはや“癒やし”より“爆発物”として認識され、関係そのものがリスク指数で測定される。これが〈他者のリスク化〉である。少年が「ありがとね、大事にするね」 と告げ、続けて 「見えないね、煙が染みて」 と視界の曇りを報告する瞬間、感謝と同時に相手を危険物として距離計算する複雑な情動が露見する。
そして2020年代、終わりなき情報過剰は「すべてを理解し切ること」を早々に諦めさせた。その代わりに浮かび上がったのが**〈ネガティブ・ケイパビリティ欲望〉だ。“わからなさを抱え続ける力”**こそが新しい才能として希求され、物語は答えより余白を祝福する。『ぼくのかみさま』で少年は「ぼくはもっと話がしたい、だから/また貴方に会いに行く」と未決の対話を自ら反復しにゆく。帰路が孤独だと分かりつつ歩みを止めない姿勢は、解決へ収束しないまま余白を維持する技芸そのものだ。
こうして敷かれた地層の上に現れるのが、筆者が提唱する〈アフター系〉である。これは“世界が一度死んだ後、その残骸から小さな営みを始める物語群”を指す。少年の掲げる狼煙は、救済を請う信号弾ではなく、瓦礫の中で「生きたいな 強くならなくちゃ」と自らに火を付ける発火点だ。応答なき神を相手取る祈りは、真空中で自壊するリスクを孕む。それでも彼は身体で煙を上げ、代理技術が保証する安全な距離を敢えて拒む。アフター系の主人公はヒーローにはなれない。だが物語の片隅で、いつ消えるとも知れない火種を護り、歩行のリズムだけで夜明けを手繰り寄せる。少年の「わかってる、帰りは一人」という自己確認は、他者との断線を認めつつも旅の継続を放棄しない—まさしく終焉後の孤児が未来を仮設する工程である。
結論・余白――夜を焦がしきらないまま、再訪の約束だけを残して
『ぼくのかみさま』は、救済の欠片を拾い集めて新たな神話を再建する歌ではない。むしろ救済が欠落したまま歩き続ける方法を、少年の狼煙という古いテクノロジーで描き直す。ここに込められたメッセージは明快ではなく、火薬の匂いだけが鼻腔に残る。その残滓をどう扱うかは、聴く者一人ひとりの手に委ねられている。「僕はまた会いにいく」という繰り返しは約束とも予告ともつかない未定義の語だ。
だからこそ問いは開いたまま突き返される。――あなたが掲げるべき狼煙は、いまどんな色をしているか。 終わった物語の灰を前に立ち尽くすのか、それとも危うい火花を抱えたまま未知の闇へ踏み出すのか。夜明け前の世界はまだ答えを持たないが、そこに向けて上がる火柱は、きっとあなただけの“かみさま”を照らし出すだろう。
※本記事は、羽生まゐご『ぼくのかみさま』(2024)の歌詞を批評・研究目的で必要最小限引用しており、著作権はすべて原権利者に帰属します。


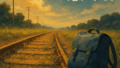
コメント