導入──泣き顔はコンテンツになる
DECO*27の『モニタリング』(2024)は、他者に見られるはずのない〈ひとり◯◯〉を実況中継する。曲冒頭の〈ねえあたし知ってるよ〉という囁きは、スマホの通知音のように私的領域へ滑り込み、涙や嗚咽を即座に“データ”へ変換する。ここには、プラットフォームによる情動の採掘と、それに自ら身を差し出すユーザーの自己展示が同時に刻印されている。本稿は、この二重化した視線を 「他者のリスク化」 と 「アフター系」 の交差点として読み解き、その背後で脈打つ 「代理技術」 と 「ネガティブ・ケイパビリティ欲望」 の力学を探る。
さて、本論を始める前に、これらの概念の内実をみておきたい。第一に 他者のリスク化──対人関係が〈喜び〉よりも〈破綻や損傷の危険〉として先に意識される傾向で、2010年代後半に顕在化した。第二に 代理技術──SNS・VTuber・AI など媒介装置を介してのみ他者と交わる姿勢であり、2010年代に一般化。第三に ネガティブ・ケイパビリティ欲望──結論の出なさや未解決の感情に耐え、それ自体を肯定的に欲望する 2020年代的感性。最後に アフター系──物語や関係がすでに終焉した後、“残骸”の上から営みを再開する作品群で、2020年代中盤以降に顕著である。本稿ではこれら四概念を相互参照しながら、曲が映し出す親密性の変容を検証する。
本論──スクリーン越しの渇望と恐れのダンス
『モニタリング』が映し出す親しさは、まず語り手〈あたし〉のあり方から始まる。彼女はスマホのレンズを通して世界を見つめ、ガラス越しにそっと触れようとし、声はデジタルの波形となって私たちの耳へ届く。一見すると安全な距離を保っているようだが、この〈あたし〉はプラットフォームが感情を測定し、広告へと変換する仕組みの中心に立たされてもいる。〈泣いてくれなきゃ涸かれてしまう〉という呼びかけは、ユーザーの涙をエネルギーに回路を動かす姿を示し、サビ頭の〈MWAH!〉は再生数が跳ねた瞬間に弾むポップアップのように響く。身体が画面の外に置かれるほど、感情だけが数字となり、その濃度は視聴者の手元で高まっていく。
集められた涙やため息は、ほどなく別の色を帯びる。それは〈他者は喜びよりも傷を運ぶかもしれない〉という、小さな怖さだ。〈舐め取って 飲み干したい〉という強い言葉は相手をまるごと取り込みたい欲望を示すが、実際に飲み込まれるのは相手の痛みや弱さばかり。泣けば泣くほど増える“しょっぱさ”は画面に粒子のようなノイズを残し、モニタリングをするほどの熱情は相手をやせさせながら続くダイエットの儀式のようにも見えてくる。
さらに〈きみはひとりだ だから歌う「ひとりじゃない」〉という矛盾したフレーズは、聴き手を“自分を演じる小さな檻”へ招き入れ、安心と不安を同じスイッチで灯す。この瞬間、慰めと破綻は紙一重となり、画面の向こう側で同居し始める。
主導権は不思議なことに語り手ではなく〈きみ〉に預けられる。かつてのヤンデレが構えていた刃物は、ここには存在しない。〈あたし〉は刃を振りかざす代わりに“引き金”だけをそっと差し出し、その先をどうするかを〈きみ〉に任せている。この揺れたままの状態に身を置く感覚こそがネガティブ・ケイパビリティ欲望であり、〈もっと泣いたって 何度だって受け止めてあげる〉という言葉が示すのは、終わらせないことでつながりを保つループの仕組みである。こうしてこの物語は、もう動かなくなった「普通の恋愛」という舞台装置を背景に、〈見守る人〉と〈映される人〉という二つの役割だけを回し続ける。崩れた舞台の破片の上で交わされるささやかなやり取り──それこそが、物語が終わった後にも芽生える アフター系 の親密さである。
小さなインターバル──関係の温度差を測る休符
ここで少し歩みを緩め、「ヤンデレ」と「普通の恋愛」、そして本作に映る関係の違いを整理してみたい。まず“普通の恋愛”は、相手との距離を縮めながらも互いの輪郭を尊重する関係を理想とする。暖かい湯船のような温度で、言葉や仕草がゆっくり溶け合う。
一方、古典的なヤンデレは沸騰寸前の熱を帯びる。好意と殺意が表裏一体となり、刃物や監禁といった直接的な手段で相手を囲い込む。触れ合いは「共にいる」ためというより、「逃がさない」ための行為として立ち上がる。
しかし『モニタリング』の〈あたし〉は、そのどちらとも異なる絶妙な体温を選ぶ。刃物は握らず、かといって安らぎの湯温でもない。彼女が武器として差し出すのは物理的な刃ではなく“視線”だ。〈見たい〉という視線が相手の周りをやわらかく囲い込み、涙や弱さが流れ出るのを静かに待ち構える。暴力はスクリーンの外部へ追いやられ、その代わりにデータ化された情動がやり取りされる——いわば暴力をデジタル粒子に置き換えたポスト・ヤンデレである。
古典ヤンデレが「絶対に離さない」と肉体で縛るなら、本作は〈ずっと見ている〉という視線で相手を拘束する。普通の恋愛が「二人で育む」営みだとすれば、『モニタリング』は「観測と被観測が互いを使い切る」ワンウェイの回路だ。そこに潜むリスクを承知でつながり続ける快楽があり、だからこそリスナーは曲が終わっても“まだ何か足りない”と感じて再生ボタンに手を伸ばす。
ネガティブ・ケイパビリティ欲望が促すこのループは、刃も抱擁も存在しない新種の擬似親密──“スクリーン越しの渇望”をもう一度味わうためのインターバルなのである。
結論──監視カメラの赤い点滅を胸に残して──監視カメラの赤い点滅を胸に残して
1990年代の自己の希薄化から2000年代のセカイ系、2010年代の代理技術と他者のリスク化――その延長線上に『モニタリング』はある。恋愛はゴールではなく、消費可能なデータポイントに解体された。泣き顔はコンテンツになり、嗚咽はループBGMになる。にもかかわらず、私たちは〈見たい見たい見たい〉とスクロールを止められず、「痛み」にコメントを付与し続ける。
イヤフォンを耳へ差し込む次の瞬間、自身の内側で稼働し続ける小さな監視カメラの赤色LEDを思い出せるだろうか。その問いだけが、この曲の再生ボタンを押し直す鍵となる。答えを出さないまま、渇望は再び画面の向こうへ流れ込む――終わらない終わりを抱えたまま。

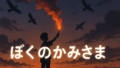
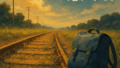
コメント