こんな人におすすめの歌詞と考察!
- この曲の「現代性」を知りたい人
- この曲の「結末」の救いを知りたい人
I. 導入──「飽和する夏」が照射する、関係性の臨界点
(※本記事には暴力・自傷を主題とする楽曲の引用が含まれます。感情的な負荷を感じる方はご注意ください)
「昨日人を殺したんだ」という衝撃的な一節から始まるカンザキイオリ『あの夏が飽和する。』は、逃避と救済の狭間で揺れる少年少女のひと夏を描く。2020年代の日本社会では、SNSトラブルやいじめ等の報道が日常化し、「逃げたい」という感情が決して例外ではなくなった。本作は“主人公になれなかった者たち”の視点で、その感情と作品に刻まれた「現代性」を救いあげたい。
読み解きの軸として二つの概念を置く。第一に他者のリスク化。他者はもはや安易な救いではなく、恐怖と不安定性の源として現れる。いじめや裏切りが横行する状況で、語り手たちの逃避はむしろ誠実な選択として提示される。第二にアフター系。既に世界が壊れたあとを前提に物語が進む構造であり、本作でも社会や倫理の基盤は失われ、主人公たちは残骸の中で生を選び直す。これは〈セカイ〉の崩壊後に感情を再構築しようとする物語だ。
そして、この二点を踏まえると、作品に潜む「共犯」と「赦し」の意味が浮かび上がる。誰もが被害者であり加害者でもある現代において、なお他者と結び付こうとする行為は、どこで臨界を超えるのか――その問いを抱えつつ、以降では歌詞構造や人物造形、終盤の展開を精査していく。
(※本稿は暴力や自殺を肯定・推奨するものではありません。歌詞引用は権利者のガイドラインに基づき最小限のみ掲載しています)
II. 本論──「他者のリスク化」と「アフター系」が交差する逃避行の倫理
まず『あの夏が飽和する。』という作品において特筆すべきは、その物語が徹底して「社会」や「正義」といった安定した制度や価値観を拒絶する姿勢にある。物語は「昨日人を殺したんだ」という一節から始まり、語り手と少女がナイフを持ち、逃避行に出るという形で進行する。このとき重要なのは、殺人そのものの正当性や理由が中心主題ではないという点である。むしろ、どのような論理であれ「正当化」が不可能である状況――言い換えれば、既に世界が倫理的に崩壊しているという前提に立って物語が展開する。ここにまず、「アフター系」の特徴が色濃く表れている。
アフター系とは、「ポスト・セカイ系」のような「実は終わっていた」という暴露構造すらも過去のものとし、「終わった世界のその後をどう生きるか」に焦点を当てる物語形式である。この構造は、セカイ系のような全能感や救世主願望を拒絶し、「世界の再生ではなく、残骸の中でどう関係を紡ぐか」という問いを提出する。『あの夏が飽和する。』では「人殺しとダメ人間の君と僕の旅だ」と表現されるように、主人公たちは再生や救済ではなく、あくまで「共犯的な共感」によって関係を築こうとする。つまり、「物語が終わった後」に残るのは希望ではなく、互いの傷を抱えた者同士の仮初の連帯である。
次に、この作品を貫いているのが、他者のリスク化という視座である。かつては家族や恋人、クラスメートといった関係性が、ある種の安心や癒しの源として機能していた。しかし現代社会では、それらの関係が一転して暴力や疎外の起点となる。いじめ、ネグレクト、同調圧力――他者はもはや「癒すもの」ではなく、「傷つける可能性を持った存在」として登場する。楽曲の中でも、〈結局僕ら誰にも愛されたことなどなかったんだ〉という一節が示すように、主人公たちはそもそも信頼に基づく関係を持つことができなかった。他者を愛せないのではなく、愛そうとしたときにリスクを背負わされてきた、という記憶の集積がここにはある。
そのため、主人公たちはただ歩き、「家族もクラスの奴らも何もかも全部捨てて」逃避する。これは「自由」の選択ではなく、「不信の果て」にある消去的選択であり、むしろこの行動は“最小限の傷で済ませる”ための倫理的判断ですらある。彼らにとって「他者」とは、信頼すべき対象ではなく、むしろ距離を取らなければ自己が損壊する対象なのだ。こうしたリスクに満ちた人間関係の中で、「自分と似た傷を持つ誰か」だけが唯一の接続可能な他者として浮かび上がる。それが「君」であり、「僕」だった。
では、彼らが目指した逃避行にはどのような意味があるのだろうか。ここで造語を挿入するとしたら、「透明な関係」とでもいえる関係性だろう。これは「友達」「恋人」といった従来の関係ラベルを拒否し、むしろ不定形なままで他者と繋がろうとする態度を示す。『あの夏が飽和する。』の語り手と同伴者は、恋人でも友人でもない。そこには明確な名前も、記号も付与されていない。ただ〈君が今までそばにいたからここまでこれた〉という、文脈に基づいた一時的な繋がりがあるだけだ。この不安定さこそが、「他者のリスク化」に対する唯一の回答である。「名前を与えること」がもたらす支配や所有を回避し、ただ共に存在することだけを肯定する関係性。それは極限状況における人間的な絆の最小単位とも言える。
さらに注目したいのは、終盤の展開である。同伴者が「死ぬのは私一人でいいよ」と告げ、自死を遂げる場面は、いかにも「映画的」でありながら、同時に本作の倫理的な臨界点を表している。ここで問われるのは「命の尊厳」ではなく、「誰かと共に死のうとした人が、最終的に一人で死ぬしかなかった」という関係性の崩壊である。物語のクライマックスは、必ずしも感動的な和解でも贖罪でもなく、ただ「君だけがどこにもいなくって」という喪失の風景へと帰着する。アフター系が描こうとするのは、まさにこの「取り返しのつかない終わり」の後に残る空虚なのだ。
こうしてみると、『あの夏が飽和する。』は、他者を信じきれない時代において、それでも誰かと関わろうとすることの困難さと、関係性が持つ倫理的な重圧を描いていると言える。そしてそれは、従来のセカイ系的な「関係の再構築」や「救済」の物語とは異なり、あくまで「関係の消尽」とその後を丁寧に描こうとするアフター系的な地平に位置している。
最後に、この物語を別の作品と比較することで、その独自性をより明確にしたい。たとえばAimerの『カタオモイ』のような楽曲は、愛されることを前提とした関係性の中で感情の揺らぎを描いている。しかし『あの夏が飽和する。』には、そのような「信頼の前提」が存在しない。むしろ信頼が存在しないからこそ、共にいることの意味が強く際立つという逆説がある。これは、アフター系が描こうとする“希望なき連帯”の核心とも一致している。
III. 結論──飽和した夏の果てに残された問い
『あの夏が飽和する。』は、物語的な救済や再出発を描かない。それどころか、希望や赦しすらどこか冷めた筆致で排除している。物語の結末は、死と少年の取り残されという“非劇的な喪失”によって静かに閉じられる。ここに描かれているのは、自意識内において終わりを迎えた世界の中で、それでも他者と関わろうとした二人の姿である。その関係は、「恋人」や「友人」「共犯者」といった言葉で容易に規定できるものではない。むしろ、それら既存の言語にすら入り込めない、透明な関係に近いものだと言える。
そして、そのような関係がもたらすものは、安らぎではなく、記憶の飽和である。曲のラストで語り手は
「六月の匂いを繰り返す」
と歌う。時間は進んでも、感情は過去に留まり続ける。飽和とは、過剰な記憶や感情がこれ以上は受け止めきれなくなった状態を指す。この「飽和する夏」とは、時間とともに流れていくはずの感情が、いつまでも留まり続け、語り手の思考や呼吸を塞いでしまうような感情の堆積なのだろう。
本稿で用いた「他者のリスク化」や「アフター系」という概念は、こうした現代的な情緒や関係性を捉えるための有効な視座である。誰かと関わることが“リスク”でしかなくなった時代において、それでも誰かの隣にいたいと願う感情は、ある意味で最もラディカルな欲望のかたちである。そして、それは物語が終わったあと、つまり正義や制度や秩序といった言語がもはや機能しない場所においてこそ描かれるべき情緒でもある。
だからこそ、この楽曲の語り手は言葉にならない問いを今も抱え続けている。
本曲の終盤に示されてるのは、物語の解決ではなく、“語り続けるしかない痛み”の始まりである。私たちはこの物語の先に、何を想像すればいいのだろうか。君が残した感情、語り手が抱える喪失、そしてこの曲を聴いた私たちが受け取ったもの――それらすべてが、この「飽和する夏」の中で静かに交差している。 結局のところ、この物語は「誰も何も悪くない」と言ってほしかった誰かの祈りであり、それにどう答えるかは、聴き手である私たち一人ひとりに委ねられている。問いは終わらない。だがその余白こそが、この物語の核心なのかもしれない。
※本稿は作品の社会的背景と情緒を批評的に考察するものであり、暴力や自死を肯定・推奨する意図は一切ありません。歌詞引用は著作権者のガイドラインに従い最小限としています。

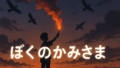

コメント