こんな人におすすめの歌詞と考察!
- 本曲の「不可能」の構造が知りたい人
- 「愛して」を繰り返す理由が知りたい人
導入:「誰かに選ばれること」への呪縛
あなたがこの曲『愛して愛して愛して』を好きになるとき、それはきっと、「誰にも選ばれないこと」の痛みを知っているからだ。誰かに見つけてほしかった過去。努力も、優しさも、笑顔さえも──本当は全部、捧げものだった。無意識に「いい子」であろうとしたことの裏には、見捨てられたくないという幼い祈りがあったのではないか。
この歌の語り手は、徹底して「見られる存在」であろうとする。評価され、愛され、誰かの一番になることで、自分という存在をようやく世界に接続しようとする。しかしそれは、願いのかたちをした呪いであり、幸福の仮面をかぶった搾取でもある。苦しくても、止められない。苦しくても、「もっと」と願ってしまう。その感情の歪みは、決して特殊なものではない。
むしろそれは、私たちが社会的に内面化してきた「良い子であること」の延長線にある。誰かに選ばれることを信じるたびに、選ばれない不安に飲み込まれる。そしてその不安こそが、語り手の「もっと愛して」という絶叫の正体なのだ。この曲に共鳴するあなたは、もしかすると、「見捨てられること」を恐れて、自分を縛りつづけてきたのではないだろうか。
※本記事では、歌詞に含まれる強い表現や感情を題材として扱っています。読み手の心情に負担をかける可能性があることをご理解のうえ、お読みください。
本論A. 構造分析:声はなぜ「断定」を避けるのか
この歌詞は、冒頭から過去を語るように始まりながら、語り手の「今」をあえて曖昧にしている。「巻かれた首輪」「人が欲しい」といった印象的なフレーズは、具体的な出来事を描くのではなく、むしろ感情の“残り香”──言葉にならない苦しさを想起させる装置として機能している。ここでは明確な時系列の流れは存在せず、時間は呪縛のようにループし、記憶と現在、願望と絶望が曖昧に溶け合っている。
視点もまた、一定しない。「あなたに告白を」と語られたかと思えば、すぐに「誰も彼も私を見てよ」と全方位に視線が放たれる。語り手は一人の“あなた”を求めているように見えて、実際には「見てくれる誰か」であれば誰でもよいのかもしれない。この不安定な感情の在り方は、「足りない」「もっと」といった反復的な言葉に象徴されている。
サビでは感情が激しく噴き出すように思えるが、そこで発せられるのはほとんどが命令や願望の形式だ。「愛して」「もっと」「止められない」といったフレーズには、「私はこう思う」「私はこうである」という断定が存在しない。語り手は語ることで自己を主張するのではなく、欲望を発露することでようやく自分がここにいると感じようとしている。ここでの言葉とは、他者に届くものというよりも、自身の存在を確認するための、静かな叫びのように見える。
本論B. フレーズ精読:「愛して」の反復が告げる飢え
この楽曲でもっとも耳に残るのは、「愛して 愛して 愛して」というサビのフレーズだろう。この反復には、単なる情熱的な愛情表現ではなく、満たされることのない飢えがにじんでいる。愛を欲する語り手は、必ずしも愛されていないわけではない。しかしその「足りなさ」は、量や頻度の問題ではなく、根源的に「受け取れない」構造に由来している。だからこそ、「もっともっと」という飽和しない欲望が、終わりなく続いていく。どういうことか。
例えば歌詞の前半にある「いい成績でしょ ねえ ねえ いい子でしょ」という一節には、承認を求めて模範的にふるまう姿勢が描かれている。だがこれは、褒められたいという欲求ではなく、「捨てられたくない」という恐れから来る自己演出である。語り手は「良い子」という記号を身にまとうことで、自分という存在を社会や他者に明け渡してしまっている。その不自由さは、すでにこの段階で顕在化している。つまり、承認を求めつつも、その承認は自己演出の延長にある自己なのだ。自己そのものではない。これが根源的に受け取れない構造となり、苦しさを生む。
それを象徴するのが「苦しい ねえ」という呼びかけだ。これは“あなた”への訴えであると同時に、鏡に向かって呟く自己確認のようでもある。苦しさの原因は、「愛されないこと」ではない。「愛されたい」という構えそのものが、語り手を内側から締め付けている。「呪いの首輪」は、誰かに無理やり巻かれたのではない。むしろ、それを自分で巻き、生き延びるためにそうするしかなかったという、ある種の絶望的な肯定がそこにはある。
後半、「汚いあなたが」と続く告白の場面では、語り手にとっての愛の対象にすら価値判断が解体されている。そこにあるのは「理想の誰か」に愛されたいという願望ではなく、「誰でもいいから私を受け取ってほしい」という叫びに近い。
「全部あげる」「全部背負ってもらうよ」という言葉には、主体性を手放してでも関係性にすがろうとする切実さが混じっている。しかし、この構えが先に述べた根源的に受け取れない構造が生み出していることは、改めて言うまでもないだろう。
このように、「愛して」という言葉は、愛されたいという感情を超えて、語り手にとっての「生存の条件」と化している。愛されなければ、存在できない。見られなければ、意味を持てない。だからこそ、「離さない」「苦しい」「幸せなの」といった矛盾した言葉が錯綜し続ける。語り手の感情は、愛情、恐怖、依存、自己嫌悪といったものが互いに溶け合いながら、静かに崩壊していくのだ。
本論C. 社会状況との照合:「良い子」という呪いと、承認資本主義の牢獄
『愛して愛して愛して』の語り手は、特定の誰かからの愛だけを求めているわけではない。その欲望は、むしろ匿名的で不特定多数に向かって拡張されていく。「あの子よりもどの子よりも 誰も彼も私を見てよ」という言葉には、比較と競争の中で生きる現代の姿がそのまま投影されている。ここでは、愛されることも承認されることも、すでに「評価」の一部となってしまっている。
この感情の構造は、SNS社会における「いいね経済」に酷似している。誰かに選ばれること、誰かに見てもらえることが価値そのものとなった時代において、人は内面よりも「良い子らしさ」や「優秀さ」というパフォーマンスを優先するようになる。それは、愛されるための振る舞いであると同時に、見捨てられないためのサバイバルでもある。
さらにこの語り手の行動は、選ばれることが“責務”となる新自由主義的な社会構造とも深く関係している。「選ばれないのは努力が足りないから」「愛されないのは自分に魅力がないから」──そうした自己責任のロジックが浸透した社会では、誰かに愛を求めることすらも、敗者のような感覚を伴う。だからこそ、「苦しい」と口にしながら、「もっと愛して」と言い続ける語り手は、敗者であることを認めないまま、その役割を演じ続ける。
このような構造は、いわば「承認資本主義」の牢獄である。他者の目がなければ存在できないという構えは、もはや一個人の病理ではない。私たち全体が、「見る/見られる」の権力関係のなかで生きるようになった結果、語り手のような存在が、特別なものではなく、どこにでもいる誰かになってしまったのである。
III. 結論:「もっと愛して」と言えたあなたへ
この歌があなたの心に残るのは、語り手の「歪さ」がどこか自分の姿と重なるからではないだろうか。愛されたい、見てほしい、選ばれたい──そう願いながらも、その願いが自分自身を蝕んでいくことに、うっすら気づいている。それでも、愛してほしい。矛盾していても、破綻していても、切実な気持ちは消えない。
『愛して愛して愛して』が描いているのは、ただの依存や狂気ではない。それは「選ばれるための生」を生きるしかなかった一人の人間の、静かな告白である。語り手は、自らを犠牲にしてまで誰かに接続しようとするが、その願いのかたちには決して単純な「幸せ」は宿っていない。むしろその叫びの中に、誰にも救えなかった孤独が、透明なまま沈殿している。
だが、だからこそこの曲は美しい。苦しみを抱えたまま、それでも声を上げる姿には、偽りのない生が刻まれている。もしあなたがこの歌に共鳴したのなら、それはあなたがまだ誰かに言えずにいた「もっと愛して」という言葉を、代わりに叫んでくれたからかもしれない。
『愛して愛して愛して』は、あなたの苦しみを肯定してくれる歌だ。「そんな自分じゃだめだ」と思っていたあなたに、「そのままでも、生きていていい」と囁いてくれる。言葉にできなかった感情が、この歌の中には確かにあった──だからこそ、この歌は、あなたの代弁者なのだ。
※本記事は、きくお氏による楽曲『愛して愛して愛して』の歌詞を批評・考察目的で一部引用しています。歌詞の著作権はすべて原権利者に帰属します。

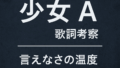

コメント