序章:存在しないものからの「語り」
本論はn-buna氏の『ウミユリ海底譚』の歌詞の意味を考察していく。しかし、その前にまず考察の方向性について語らなければならないだろう。
ここでは『ウミユリ海底譚』が誰のための、あるいは誰による曲なのか、ということを考えていきたい。これは作詞や作曲者という話ではなく、どのような視点からのものなのか、という意味においてである。
この点についてはYoutubeのコメント欄などを眺めるとわかるように「自殺をしてしまいそうな人の曲」という解釈が一般的らしい。なるほど確かに「空中散歩のSOS」や「消えない君を描いた」というフレーズからは、生死にかかわるような緊迫感が宿っている。
ただ、本論ではこの解釈に追随することはない。結論をいえば、この曲は、死んでいるわけでも、生きているわけでもない存在からのものだと解釈ができる。 どういうことだろうか。それをこれから見ていこう。
第一章:「海」と「空」の舞台装置について
この曲には生殺与奪に関わる独特な緊張感が宿っていると前節では述べた。前述したフレーズが、そのように想起させるのだと思う。だが、実はそれだけではない。
本曲にはタイトルがそうであるように「海」や「空」という言葉が多用されている。この「空」と「海」から広がる世界観が、本曲のフレーズに危なっかしさを宿すのではないだろうか。「空」も「海」も人の命などあっという間に飲み込んでしまう場所でもあるからだ。
だが、この「空」や「海」という舞台装置には必然性がないことがわかるだろうか。もし語り手が「自殺してしまいそうな人」であるならば、舞台はビル街でも自室でも屋上でもいいはずだ。繰り返しになるが、この曲の背景にある風景が「空」「海」である必要性は語り手が「自殺してしまいそうな人」である限り存在しない。翻っていえば、私たちは、この必然性を何らかの仕方で発見しなくてはならないのだ。
ところで、更に抽象的に「場所」についての話をしよう。聖地という言葉があることからわかるように人は昔から「場所」に意味を見出してきた。「この場所といえば○○の場所」というように「場所」は何かしら象徴でもあったのだ。
歌でいえば吉幾三の『俺ら東京さ行ぐだ』は、そんな「象徴」の最たる例だろう。「東京」は地方在住者にとって「希望」にあふれた場所だった。他にも「渋谷」といえば「若者の街」と言われるのも、この「場所」=「象徴」の例だ。
では、ここまで見てきたところで話を戻そう。
『ウミユリ海底譚』で歌われている「海」や「空」は何を象徴しているか。そこで思い出してほしい。この曲がボーカロイドというインターネットカルチャーから生まれたことを。 「ただの言葉遊び」だと言われることを承知で続けてしまえば、インターネットには「海」と「空」を同時に結びつける場所であったはずだ。「ネットの海」というのは言葉通りであるし、「空」についてもコンピュータ技術に関することで「クラウド」(=雲)という言葉があるほどだ。インターネットは「海」と「空」のどちらの紐づけも可能にする。
第二章:「ローカル」と「クラウド」もしくは夢による関係性について
そうであるならば『ウミユリ海底譚』の語り手は、そんなインターネットに関わりの深い存在でなければならない。もう言わずともわかるだろう。この曲の語り手、誰の視点からの曲なのか。それは、初音ミク。ひいてはボーカロイド全般から視点から歌われたのが本曲なのだ。
このように解釈すれば、冒頭の「僕の歌を笑わないで」というフレーズの意味が明晰になる。これはそのままの意味なのだ。さらにいえば前述したように「空」を「クラウド」とした場合、対極の「海」は、ボーカロイドのソフトがインストールされる「ローカル」ということになるだろう。
そのように考えれば「揺らぎの中 空を眺める」というフレーズも、アップロードされ、多くの人に聞いてもらうことに憧れるボーカロイドからの視点という風に考えられないだろうか。
そして、ここで同時に「君」の正体も確定する。「君」はクリエイターのことを指しているのだ。そう。この曲は全体として「君」というクリエイターを励ます「僕」であるボーカロイドという関係性によって構築されている。
いくつか例を挙げよう。
まず「夢の続きが始まらない/僕はまだ忘れないのに」という箇所。
ここでいう「夢」は誰のものか。言わずもがな「君」である。「君」は「僕」を通じて作品を作ろうとした。おそらく、たくさんの人に聞いてもらうという夢があったのだろう。しかし、その夢は頓挫した。原因はわからない。
そんな「君」は夢を忘れようとしている。だが、それを阻む存在がいた。それが「僕」=「ボーカロイド」である。だからこそ「僕はまだ忘れないのに」と言う。
さらに続けよう。この関係性を示しているのは別の個所にもある。
例えば「君の嗚咽」という歌詞のあと「君はここで止まらないで」と続く部分。これはボーカロイドからクリエイターへの励ましなのだという風にも考えられる。 その励ましの結果なのだろう。この曲は最後「あの空に溺れていく」とある。「僕」=「ボーカロイド」、「君」=「クリエイター」とするならば「あの空に溺れていく」というのは、完成物が無事にアップロードされた、「ボーカロイド」「クリエイター」の二人にとって一旦のハッピーエンドを迎えたという意味になるのではないだろうか。
結論:「人ならざるもの」の新風
いかがだっただろうか。
いささか突飛な考察であることは筆者自身も自覚しているところだ。しかし、それなりに説得力を持たせることができたとも思っている。
本曲は、ボーカロイド文化が生んだ楽曲、いや、ボーカロイド文化が無ければ存在しなかった曲だろう。その理由はここまで読んでくれた読者諸氏にはわかるはずだ。 人ならざるものからの視点を曲にできるボーカロイド、その結晶としての『ウミユリ海底譚』。この曲が多くの人に聞かれていることはすでに、新たな視点の音楽文化の萌芽ともいえる。ここでは詳細を語るわけにはいかないが、先のような視点が様々な分野での新風になることは、いずれ時代が証明するだろう。この曲は、その一歩であり、結実であり、通過点でもあるということは最後に申し上げておきたい。
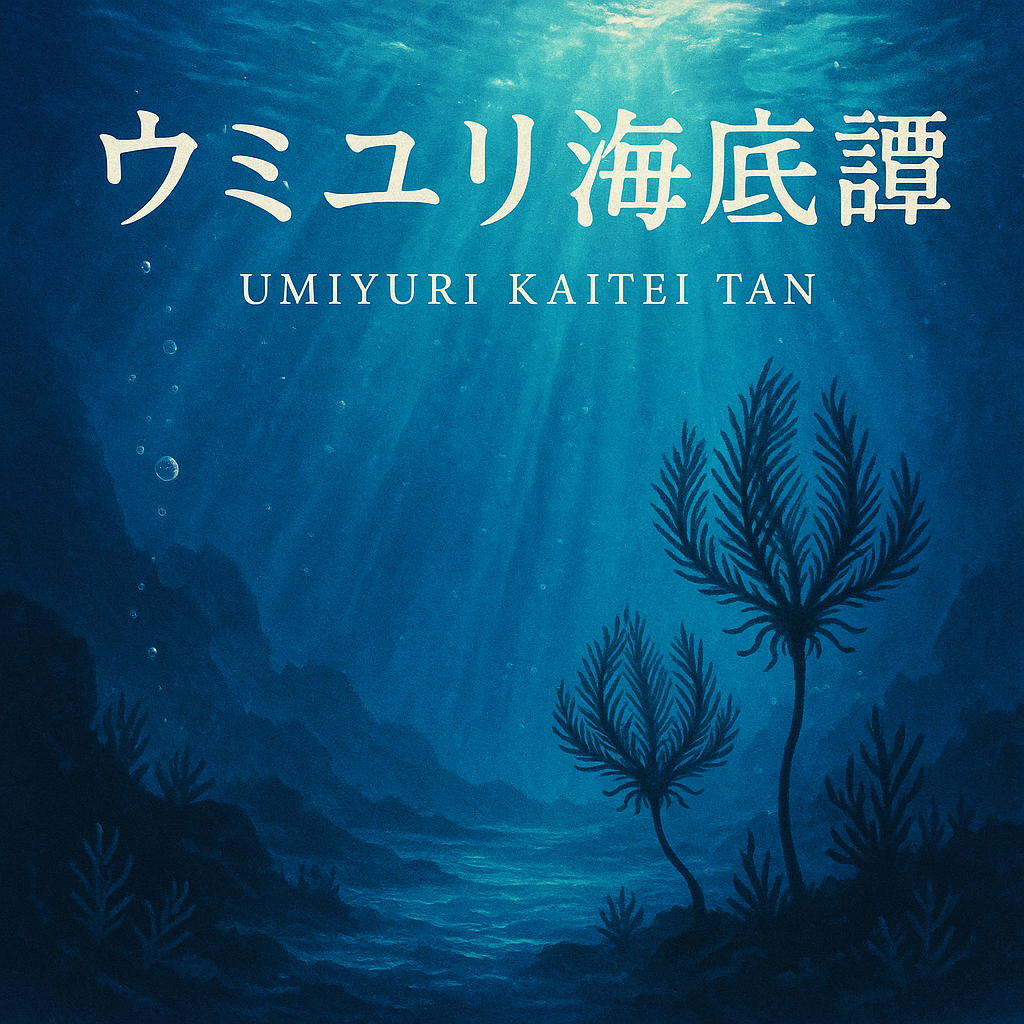

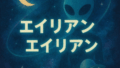
コメント